 「お気に入り」登録を解除
「お気に入り」登録を解除
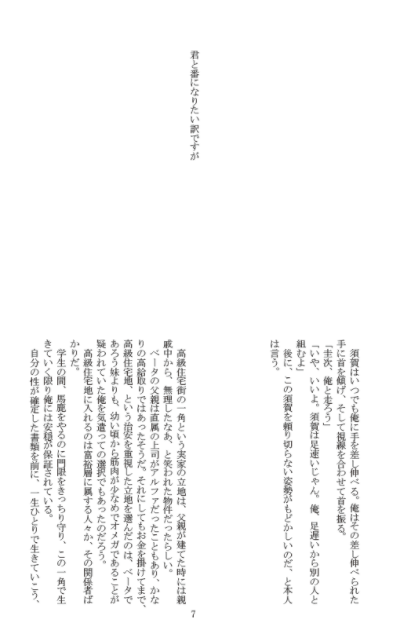
A5サイズ二段組44ページ
web再録
「君と番になりたい訳ですが」(約1.4万字)(R18)
「I Saw ── Kissing Santa Claus」(約0.4万字)
書き下ろし
「君と遠回りがしたかった」(約0.7万字) …… 本編直後のデート話
「陽だまりを手で掬ったら」(約0.9万字)(R18) ……本編後の発情期話
通販について
紙版→在庫分も含め完売しております
電子書籍版(BOOTH)→https://sakamichi31.booth.pm/items/3212485
※BOOSTは電子だとお礼のペーパー同封したりもできないので、基本的に支援のお気持ちだけで十分です。
頂いた分については普段の小説執筆のための事務品やソフト代、参考書籍代などに有難く使わせていただきます。
電子書籍版(楽天Kobo電子書籍)→https://books.rakuten.co.jp/rk/28af95e36cea3677a376b56a63ccea72/
電子書籍版(BOOK☆WALKER)→https://r18.bookwalker.jp/de9059eca8-29f3-4648-8aef-2418939b51dc/
電子書籍版(メロンブックス)→https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=1682011
「君と遠回りがしたかった」 サンプル
須賀と付き合うようになって、学校回りが騒がしくなるだろうと思っていたが、想像していたよりも静かに学校生活は再開した。
須賀が手を回した部分もあるのだろう、『オメガだったんだ』という感想こそあれど、それだけだ。色々と心配しがちな須賀が常に近くにいる状況で、俺の気に障ることを言うような無鉄砲な人間もいないようだった。
そして番持ちというものは、周囲の誰にとっても安全なものらしい。この学校にもオメガがそこそこいるようで、声を掛けられたり、特有の相談を受けるようになった。今度は俺が支えになってやれれば、と柄にもないことを思い始めている。
その日も須賀家の弁当を受け取り、蓋を開けて色鮮やかなそれを目で楽しむ。
弁当は両親同士の話し合いの元、俺の分も須賀と一緒に用意して貰えることになった。須賀が休みの日は、登校の途中で寄ってくださいね、とのことで、至れり尽くせりである。
当初は両親も、向こうに悪い、という意識があったようだが、須賀の両親に『もともと圭次くんは息子同然でしたから』と話をされてからは、俺の面倒を見る人が増えた、くらいの感覚だ。須賀家には入り浸っていたから、今更な話かもしれない。
わくわくしながら物珍しい料理を眺め、箸を取った。毎日の弁当を楽しみにしている俺を、毎度のごとく須賀は目を細めて見ている。
「圭次くんよ、今週末デートしよう」
「いいけど。どこ行くの?」
意識は完全に料理へと向いていて、卵焼きを摘まんで齧り付く。視線を上げた先の須賀の目は丸くなっていて、ストローが口から落ちそうだ。がじ、と鋭い牙がストローを支えるように噛み付く。
少し痛いんだよなぁあれ、と関係ないことを思いつつ咀嚼していると、須賀は紅茶のパックを机に置いた。
「……デートしてくれんの?」
「番だから。デートするけど」
「そういう反応は何か嫌だ」
年頃の少年のような面倒さに、返す言葉に迷いながら咀嚼で答えを引き伸ばす。昔から偶にこういう反応があったような気もしたが、この面倒さの由来が恋心だったとは驚くばかりだ。
「須賀とお出掛けすんの純粋に楽しみだけど。そう思うのはだめ?」
いじけている表情を見上げると、須賀の瞼が動く。腕が伸び、頭をわしわしと撫でた。そう思うのはいい、ということらしい。
ハンバーグを割って口に入れる。デミグラスソースの味が口に広がると、自然と頬が緩んだ。
「動物園行かない?」
「行きたい!」
「美術館もいいかなと思ったけど、お前はそうだよな」
頬をさらりと撫でて過ぎた指先を見返しながら、別に美術館も良かったけど、という言葉を飲み込んだ。須賀がもし行きたかったのなら、俺だって付いていくのはやぶさかではないのだ。
番は、俺からの愛を自覚していない気がする。
「じゃ、土曜に迎えに行くから」
時間を決めると、須賀はようやく自分の弁当に手を付け始めた。
目の前のアルファと番になったと言ったら、家族全員がまあそうだろうな、という反応だった。須賀が近くにいることを許して分かりやすく番として求められていながら、俺がそれに素で気づいていないものだから言おうにも言えなかったようだ。
周囲から俺が須賀を好きなように見えなかったということは、本人もそう思っているんだろう。
たぶん、と前置きした好きを、もっと伝えたほうがいい気がした。デートの誘いを受けたり、デートを楽しみにしていると伝えただけで驚くなんて、あまりにも須賀が気の毒だ。
手元の箸を止め、食事をする須賀を眺める。
「須賀。あのさ……」
「ん?」
あまりにも唐突すぎるか、と、話題を美味しい料理の話にすり替えた。デートをするのなら、その時に言えばいいのだ。
楽観してそのチャンスを逃した俺は、デートまでの間、どういう話の流れで好きだと伝えればいいのか悩むことになる。
「陽だまりを手で掬ったら」 サンプル
誠が生まれてから、変化は目まぐるしかった。
俺もだが優征もまた育児には慣れておらず、お互いの両親に頼りつつも子どもは着々と成長していく。
誠が腹にいた間に発情期は起きなかったのだが、子どもがある程度育てば、個人差はあれどまた戻ってくる。もしそうなったら俺の両親にしばらく見てもらって、俺と優征と二人だけで数日過ごそうか、という話に落ち着いていた。
普段から頼り切っている所為で、誠も『お祖父ちゃんとお祖母ちゃん』が好きだ。お泊まりをさせてみても何事もなく、迎えに行けば上機嫌なまま腕に収まる。
感情の起伏も大きくはなく、優征は通じるものがあるのか、アルファかもな、と呟いていた。
そうやって日々を過ごしていた中で、体調に変化が起きたのは朝方だった。
目を覚ますと、覚えのある違和感が全身に満ちている。額を押さえ、胸を押し上げて呼吸をした。身体が熱く、妙に高ぶっている。
「優征」
隣でまだ眠っている身体を揺り動かすと、寝起きの良い番はすぐに目を開けた。髪の隙間から覗く鋭い目元は、まだ角を持たない。
ぼんやりした様子でこちらを見る優征に、縋るように言葉を掛ける。
「たぶん、発情期っぽい」
「あぁ…………」
寝起きだというのに、優征はすぐに事態を認識したらしい。身を起こすと、一瞬だけぼうっと虚空を見る。そして俺を引き寄せ、首元に鼻先を寄せた。
すん、と息を吸う音が、至近距離でする。真剣な表情は見慣れていても美しく整っていて、何度も彼が番であることを疑ってしまう。
「ああ、間違いないな」
優征は枕元にあった携帯電話を引き寄せると、すぐに俺の両親と連絡を取り始めた。幸いすぐに返信メッセージがあり、優征はまだ眠っている誠を連れ、お泊まりセットを持って俺の家に託しに行った。
両親の都合が悪ければベビーシッターを手配する予定だったが、見知った相手に頼めて助かった。
手首に鼻を近づけ、匂いを嗅ぐ。俺には自分の匂いの変化よりも、この熱っぽさの方が分かりやすい発情期の指標だ。
しばらくベッドでごろごろしながら待っていると、優征が帰ってきた。
「誠、階段の上り下りもしたのに全く起きねえでやんの。ありゃ大物になるな」
「そうそう。よく寝るんだよなあ」
誠は身体も平均より大きく、体調を崩すことも少ない。けれど、その代わりなのか、よく食べ、よく眠る。かといって、誰かが側にいれば盛んに動きもする。人が側にいればはしゃいでもいいことを、察しているようですらあった。
クローゼットから優征が着替えを出してくれ、パジャマを脱いで袖を通す。隣で優征も着替えていたが、その裸が見える度にじっとりと視線を這わせた。早く齧り付いて、齧り付かれたい。発情期以外でも性欲はあるのだが、この時期は特に顕著だった。
大きなバッグに着替えを詰め込むと、優征は執事の鵜来さんにこれからの予定を話しに行った。その割には元々相談していたのか、すぐに戻ってきて用意した着替えのバッグを肩に掛ける。
「大丈夫そうだから、移動するか」
「ぼーっとしてる内に準備が全部終わった……」
俺が茫然としていると、優征は腕を伸ばし頭を撫でた。視線の前で髪が揺れる。
「体調悪いんだからぼーっとしとけ。借りてた部屋に着いたら、もうあとは寝るだけだから」
屋敷を出て車に乗り込む間、使用人の誰とも会わなかった。目元も潤んでいるだろうし、体調が悪い姿を見られたくもない。助かった、と車のシートに背を預け、脱力した。
エンジンが掛かる音がして、車は滑らかに出発した。車の免許が取れる歳になった時、優征はすぐに免許を取りに行っていた。色々とこれまでも役に立ってきたが、今回はまさに助かったと言う他ない。自分と番しかいない空間は、何処よりも安全な場所だ。
まだ俺のフェロモンが強くないのか、優征も引き摺られているようではない。前を見る横顔は平然としたものだ。
「途中、美味いもん買っていこうな。どうせ、食うかヤるかだし」
「お肉食べたいなー」
「お前、そういう時だけ幼いトーン作るんだよな……。いっぱい買ってやるけど」
途中で二十四時間営業のスーパーに立ち寄ると、俺を車に待たせ、食材を両手に提げて帰ってくる。覗き込むと、すぐに食べられそうな食品と、おねだりした肉が入っている。
今日中はさほど酷くならないだろうし、食を楽しむ余裕もあるだろう。
優征が借りているマンションに辿り着くと、少し前に来て準備をしたのだそうで、生活用品はほとんど揃っていた。冷蔵庫に食品を入れ、足りないものはないか確認するが、経験上、優征が手配したもので不足があるはずもなかった。
大丈夫そうだな、と確認し直した優征は頷き、俺はその間ソファに座って寛いでいた。
「圭次、今日の夜。すき焼きと焼き肉どっちにする?」
「すき焼き!」
俺が大声で言うと、優征は笑って了解してくれた。寝てろ、と言われて、大人しくソファに沈み込む。
大きな身体が静かに歩いている足音がして、少し後で、身体を柔らかい感触が覆った。与えられたブランケットを指先で引き寄せる。一度ソファが沈んで、また反動で浮き上がった。
指の背で、頬を撫でられる。くすぐったさに笑い出すと、少し低い笑い声が重なった。

