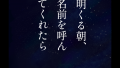「お気に入り」へ追加
「お気に入り」へ追加
【人物】
兎毛 松汰(うげ しょうた)
ホノマガ
「私は貴方の恋人です」
「違うよ。俺とお前は寄生種と宿主だよ」
ヒトならざる『それ』は俺に向けた前足らしきものをくたりと床に伸ばし、ごろりと寝転がってグロロロ、と叩き潰されたような声を上げた。
俺が帰宅すると『それ』はのそのそと床を這って俺に近づき、俺の足からくるくるとマジックテープの付いた猿のぬいぐるみのように回転しながら首にしがみつく。
初夏の今日、体温を逃がすべき場所に巻き付かれると都合が悪い。俺は『それ』を首元から引き剥がすと、腹回りに巻き付け直した。
『それ』は腹のあたりからシャツの裾を捲り、腕らしきものを伸ばして臍をぐりぐりと押し始める。
すこし遮るような感覚の後、ずぼっと腹が貫通された感覚があった。
「ホノマガ。少し太ったか?」
「夏は養分が必要なのです」
以前よりも重くなった『それ』ことホノマガという生き物は、いずれかの星の宇宙人である。その星の宇宙人は、別の生き物に文字通り張り付いて生きる。
ホノマガの本来居るべき星には、仲の良い別の種族がおり、普段はその別の種族と生きるのが慣例化しているようだ。
しかしホノマガという個体は、日本に観光旅行に来ていた母体が地球で出産を迎えてしまったことから、慣例を破らざるを得なくなった。
張り付くための別種族がその場にいない状態で生まれたホノマガは、母体が運ばれた病院内で同時刻に生を享けた俺に張り付くことに決めたらしい。
産み落とされたばかりの俺に、よく分からない生物が張り付き、どうやっても剥がれようとしなかったあの一件は、ホノマガの種族の研究書に事例として書き残されている。
それから二十年、俺とホノマガは寄生種と宿主として地球で生活を続けていた。
定期的にホノマガの種族の研究に協力はしているが、ホノマガにとっても人権らしきものが存在しているらしく、生活を脅かされるほどの干渉を受けることはない。
俺は冷蔵庫を空け、冷えたミネラルウォーターを取り出す。冷蔵庫内は朝見た時よりも随分中身が減っていた。
野菜に肉が少々、買ってあった炭酸飲料も減っている。
「炭酸ジュースって美味いのか?」
「はい。シュワシュワと口の中ではじけるもので。面白くてつい飲みすぎてしまいます」
「ふーん。野菜は買い足しておくな。何がいい?」
「トマトが必要です。ピーマンも必要です。カボチャも頂きたい」
我儘だな、とつい口に出すと、ホノマガの足でべしべしと背を叩かれた。
作り置きされているらしいカレーが入った鍋は、鍋ごと冷蔵庫に仕舞われている。
ホノマガの知性について研究者が口を揃えて高度な、と言い切るあたり、なんで料理ができるんだろう、という疑問は愚問なのだろう。
グラスに冷えたミネラルウォーターを注ぎ、ぐい、と飲み干す。
臍を通じて、腹膜の先にある臓器と連結しているらしいその腕は、ぐにゃりぐにゃりと形を変え、俺の身体へ何かを送っている。痛みもなければ、臍以外の違和感もない。
「私にも水を頂きたい」
ペットボトルを傾け、横に回り込んできたホノマガの頭らしき部分に少しずつ掛ける。水は零れることなく、頭部に吸収されていった。
ペットボトルの蓋を閉め、冷蔵庫に仕舞う。ホノマガは満足そうにグロロロ、と喉を鳴らした。
喉を鳴らしているようにはとても聞こえないが、本人がそう主張するので大人は妥協せざるを得ない。
「松汰。睡眠が不足しているようです。昼寝をしましょう」
俺の身体をまさぐって何事かを汲み取ったのか、ホノマガはそう言い出した。俺は見たい映画があったので、頷いてソファに向かった。
ごろりと身を転がし、ホノマガを潰しながらソファに横たわる。ホノマガはぶつぶつと文句を言いながら、俺の腹に這い上った。
リモコンを片手に、録画していた映画を流す。
エイリアンを撃ちまくるB級ホラーアクション映画に対して、ホノマガは不機嫌そうに俺の胸元に耳を付けた。
ホノマガは自称猫の姿をしている。耳があり、鼻らしきものがあり、目らしきものがあり、前足と後ろ足がある。
けれど、猫と呼ぶには、構成する要素はそれだけだ。
猫のようにふさりとした毛はないし、真白かったりキジトラのような柄がある訳でもない。
黒色に近い体色と、触れるとゴムのような弾力を返す肌。哺乳類と言うよりも、両生類のような生き物だと思う。
テレビの中で撃ち殺されるエイリアンに視線を戻し、うとうとと眠りに落ちていく。腹の上の重みは俺が眠りに落ちるまで、その場を動くことはなかった。
起きた時には夕方だった。
彩度が落ちていく夕焼けを眺め、ぼんやりとテレビに視線を向ける。俺が眠り込んだであろう場面で器用に一時停止状態にされていた。
ぼうっと画面を眺めていると、ことことと鍋の中身が煮える音がした。狭い室内は、すぐにキッチンに視線が届く。
その場に立っていた男は、固い表情で鍋に視線を向けていた。
「ホノマガ。飯か?」
「そうです。カレーを温めています」
男……ホノマガが形を変えたその姿は、猫と主張する姿がいびつであることが嘘のように、整った顔立ちをしている。
人型を取りたいと言ったホノマガに、映画で勉強させたのは失敗だった。ホノマガが人型を取り始めたときには、その場に立っていたのは絶世の美形であった。
薄い金髪、蒼の瞳。長い睫に透けるような肌と、ほどよく筋肉の付いた長身の男。
時代を問わず、世代を問わず、映画で美をかき集め、再構成されたその美形を、俺が外に出すことができなくなったのもその時だ。
これほど美しい人間がいるはずがない。はっきり言って人と呼ぶには異様なのだ。間違ってもスーパーでトマトを買ってはいけない。
猫があれほど下手なのだから、人を真似るのも下手だろうと高を括っていたのだが、猫は下手なまま、人型は美形なまま変わることはない。
少し美形じゃなくしてくれ、と言ったのだが、ホノマガは研究の成果であるその姿を気に入ってしまった。この姿の修正はしない、と宣言されてしまっている。
ホノマガはご飯を盛り、カレーを掛け、グラスに水を二つ注いだ。
そのうちの一つのグラスを持ったまま近寄ってきて、俺に差し出す。
「ありがとう」
ホノマガは引き返して取ってきたカレー皿を机に置き、スプーンで行儀悪く米粒とカレーを掻き回した。全体の色が均一化されると、ようやくカレーを口に含む。
俺は匂いだけを吸い込み、グラスに口を付けた。
「美味いか?」
「美味しいです。たくさん養分が取れて都合もいい。夏ですから、人間には養分が必要なのです」
ホノマガは大口でカレーを口に入れる。齧り付くように、二人分を食べ尽くすつもりのように。
「特に貴方のような、養分を自力で摂取できない個体は、養分を十全に整えなければすぐに体調を崩すでしょう」
そうだねえ、と俺は自棄になったように水を飲み干した。
俺が生を享けたあの日、生まれた俺は死にかけていたのだと言う。多くの臓器が上手く動かず、医者達が対応を話し合っていた矢先に、ホノマガが俺に張り付いた。
ホノマガは引いても押しても俺から離れることなく、流暢に言葉を発し始めた。
『この個体は単体で生きていくことが難しい個体です。私が共に生きましょう』
ホノマガは野菜でも肉でも、噛み砕き嚥下し、それらを栄養素として抽出することができた。そしてそれらを別の個体に送り込むこともできた。
死にかけていた俺が落ち着いて眠り始めた時、呆気にとられていた周囲は慌ただしくホノマガの存在の調査を始めた。
「寄生種を全力で生かすとは、心の広い宿主もいたもんだ」
「我々は元の星では慈悲深い種族だと言われています。ただし、我々の認識とは齟齬があります」
スプーンを口に入れ、咀嚼し、嚥下する。ごくり、と作られた喉が鳴った。
「我々は、我々が居なければ生き得ないような存在を、狂ったように愛すのです。それは慈悲深いとは言わない」
蕩けるように微笑んだ男は、やがて皿を空にする。
立ち上がってシンクに食器類を置き、人の仕草そのままにそれらを洗い清め、布巾で水気を拭き取り、片付ける。
そこまでしてようやく、身体の形を自称猫の形状に戻した。
ばさばさと降る洋服を器用に畳むと、それらを頭の上に乗せ、洋服ダンスへ運ぶ。
畳んだ洋服を仕舞い込むホノマガの行動をぼんやり見守りながら、グラスに視線を落とす。
「お前は俺を愛しているか」
「はい。貴方を生かすこと、それが私の愛です」
俺は他者には、ホノマガの種族との共生者と呼ばれている。
俺が食事を取るときに、簡易栄養食のような謎のパックに入れられた飲み物を口にするのも、その所為だと思っている。
中身はただの水でしかない。
俺は共生しているのではなく、ホノマガという宿主に生かされているだけの、ただの寄生種である。俺単体では、栄養を得ることも、生きていくこともできない。
「俺も愛してるよ。ホノマガ」
今日は抱いてくれるのか、と問うと、暑いですから、と端的に断られた。
そう言う猫らしき生物は、黒くてゴムのような感触で、髭も毛もなく、とても猫とは呼べそうにはなかった。
宇宙人は、今日も愛情表現のように俺の腹の上で、グロロロ、と喉を鳴らす。