 「お気に入り」へ追加
「お気に入り」へ追加
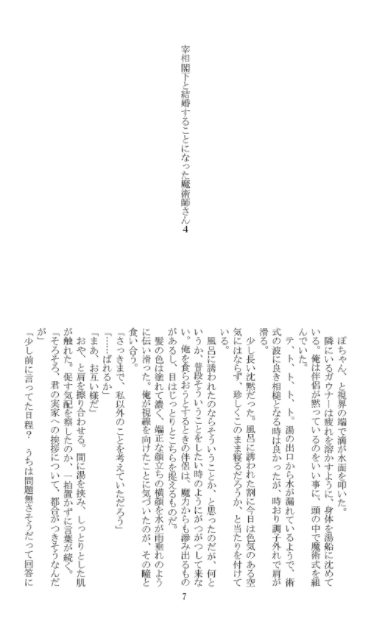
A5サイズ二段組90ページ
web再録
「宰相閣下と結婚することになった魔術師さん4」~実家帰省道中編~(約5.5万字)(R18)
「隊長と元相棒の魔術師さんと星の犬(SS)」
「宰相閣下と魔術師さんと料理長のふわふわたまごやき(SS)」
書き下ろし
「宰相閣下と魔術師さんと媚薬騒動」(約0.7万字)(R18)
「宰相閣下と魔術師さんと再会の約束」(約1.8万字)
通販について
紙版→書店委託期間を終了しておりますが、定期的にとらのあなの取寄販売に登録しております、アナウンスはX(twitter)にて行います。
電子書籍版(BOOTH)→https://sakamichi31.booth.pm/items/3109037
※BOOSTは電子だとお礼のペーパー同封したりもできないので、基本的に支援のお気持ちだけで十分です。
頂いた分については普段の小説執筆のための事務品やソフト代、参考書籍代などに有難く使わせていただきます。
電子書籍版(楽天Kobo電子書籍)→https://books.rakuten.co.jp/rk/64c930cf904a37eb91bad43a93a94ec7/
電子書籍版(BOOK☆WALKER)→https://r18.bookwalker.jp/de3b42494e-fc26-4796-823b-1fdf6030bf1a/
電子書籍版(メロンブックス)→https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=1682010
「宰相閣下と魔術師さんと媚薬騒動」サンプル
その包みは、昼休みにこそこそと近づいてきたヘルメスから手渡されたものだった。固いものが入ったそれを受け取りつつ、にこにことしている部下を見返す。
東の国特有の意匠が使われた包みは、開くと紅色の飴が入っていた。
「何だこれ?」
見た目は何の変哲もない飴なのだろうが、ヘルメスがこうやって渡してくるということは、自作であるに違いない。
よくぞ聞いてくれました、とでも言いたげに胸を張ると、問題児の部下は得意げに口を開く。
「媚薬ですよ」
彼の奇行に慣れた俺でさえ、はい? と聞き返してしまった程には、その贈り物は突拍子もなかった。
ヘルメスが言うには、食用の豆を葉で覆ってしばらく保管し、砕いて砂糖と混ぜたものらしい。つまり人体に害はない食材しか使っていない、という主張であったのだが、作った当人は実験によって設備を破壊している常習犯である。
自分で食べたか? と尋ねたのだが、
『悪影響があれば次の実験が止まりますので、僕自身では試さないことにしています』
さも正論であるかのように堂々と言われるものだから、俺はそっかあ……、と勢いに呑まれて黙り込んだ。
『俺に試してほしい、てことか?』
『既婚者ですので問題ないかと』
まかり間違って事故でも起きれば大問題なのだが、ヘルメスは実験に自信を持っているようで、よろしくお願いしますね、と俺に飴を押しつけて去っていった。
職場で捨てるのを見られては気まずい、と屋敷に持ち帰ってはみたが、開き直してもその毒々しい色を食べる気にはなれない。じっと眺めて、そっと包み直す。
俺が飴の包みを握っていると、近くを執事のアカシャが通りかかった。
「おや。東の国の包み紙ですね、お土産か何かで?」
部下から媚薬を貰って、などと言えば、大事になりかねない。誤魔化し笑いと共に、口を開いた。
「そう。お土産なんだ」
ろくでもないが、部下からの土産と言えなくもない。俺がそう言うと、アカシャはそれはいいですね、と罪悪感を覚える笑みを返した。
このまま捨てては、外から戻ってきたニコが匂いで探り当ててしまうだろうか。何か袋になるものはあったかな、と周囲を探すが、適当な袋はなかった。
袋を求めて階段を上がり、元は自室だった部屋を眺める。
おそらく、本を買ったときの紙袋が何処かにあるはずだった。本の山を積み変え、いい機会だと読み終わった本も仕分けする。山が整った頃、本を買った時の紙袋が本の下に押し潰されているのを見つけた。
紙袋を引き出し、脇に置くと、残った山の整理をある程度まで続けた。
これでぐるぐる巻きにして捨てよう、と紙袋を手に、トントンと階段を下りる。熱中していて気づかなかったが、ガウナーが帰宅していたようで、金髪の後ろ姿が見えていた。
「おかえり。ガウナー」
背後から両手で抱きつくと、手の甲を覆うように掌が添えられた。ふふ、と広い背に顔を埋めて甘えていると、ガウナーの空いた手のほうでかさりと音がした。
背から顔を出して手元を覗き込むと、部下のヘルメスから受け取った飴の包みがそこにはあった。
「あ、それ」
「お土産なんだってな。ありがとう」
ぱくり、と止める間もなく飴は伴侶の口に消え、わああ、と俺の間抜けな叫び声が場に響いた。
「ちょ、待って。それ、俺が土産……じゃないけど、で貰ったもので、ガウナーへの土産って訳じゃなくて。あの…………、それ、媚薬で」
「は? なんで君はそんなものを土産に」
怪訝そうな顔をするガウナーに、違う、と必死に手を振る。違うんだよぉ……、と萎れながら、部下からの無茶ぶりからアカシャとの不幸な齟齬を語ると、ガウナーはようやく事の顛末を理解したようだった。
「勝手に食べてしまったのは悪かったが、特段、変な味はしないがな……」
もごもごと口を動かしているガウナーに、吐き出すよう訴えるのだが、部下を詳しく知らないガウナーは、その飴の危険性を分かってはいないようだった。
俺だけがひたすら慌てながら、回らない口を必死に動かす。
「部下の……ヘルメスは実験が好きなんだけど、作った物体はよく爆発するし、そういう奴だから、危ないし捨てておこうって」
「ああ、なるほど。味は普通の飴だが、表面の堅い部分が溶けて、中身の液体らしきものが口の中に広がっているな」
「うわぁああ、吐いて!」
水を含ませて水場で吐き出させると、俺の言葉に従いはしたものの、当の本人は少し残念そうにしていた。重く息を吐き、吐き出された欠片を拾って紙袋に放り込む。
口を固く縛り捨て終えると、一仕事終えたような倦怠感が身体を襲った。
「体調は平気か? 何かあったら俺が病院まで運ぶから」
「いや。別に何事もなさそうだが、薬として効いてくるのならもう少し後だろう。食事は軽めにしておくか」
ガウナーは何が起こるとも思っていないようだ。
だが、部下のこれまでの所業を詳細に知らない者からすれば、何もそこまで、といった様子なのは分かる。一度、政策企画課で実験でもさせればいいだろうか。
釈然としないながらも、食卓について食事を始める。
アカシャはあの包みが俺からの土産である、と誤解してガウナーに伝えたのみだったようで、折角の土産なのだから腹が減っている間に食べた方が美味しいだろう、と手に取ったそうだ。
部下のこれまでの所業をあげつらってみたが、爆発するような物質と食べ物ではまた違うのでは、と逆に擁護されてしまった。
「失敗の多い人間が作った媚薬というのなら、いつも通りに事が進めば、効果を齎さないんじゃないか?」
「まあ……。そう、かな」
釈然としない、という顔をしている俺と共に、ガウナーは軽く食事を済ませた。休み前日であったから酒を飲むかと思ったが、飴の件もあり控えることにしたようだ。
食器を片付けて立ち上がり、思い出したように腕を組む。
「風呂いく?」
「……ああ、媚薬の効果も確かめたいしな」
身を屈め、額に唇が落ちる。
ガウナーの体調に悪いところはないようで、杞憂だったのかな、と思いながら風呂に入った。魔術も使っておこう、と褥のための魔術を起動させると、気が利くとでもいうように腰を抱かれ、身を擦り付けられる。
風呂にいる間からべたべたとくっつきたがる様子に、違和感がない訳ではなかったが、以前もそういう日があったか、と思い直した。
風呂から上がって化粧着を羽織ると、廊下を抜け、玄関の扉から顔だけを出す。玄関前ではニコが寝そべっており、身体を反転させてこちらを見た。
「ニコ、今日は一人で寝られる?」
わっふ、と元気な返事に対し、両手で捕まえて褒めた。
一緒に寝たい時は、こちらがどうあれ執拗に転がってねだる。大人しく寝転がっている様子から察するに、星が綺麗な外で過ごしたかったのだろう。
扉を閉めて振り返ると、ガウナーに捕まった。背に腕が回り、すんすんと鼻先を首筋に擦り付ける。
「今日、やたら甘えただなあ」
「…………そう、だろうか」
残った水滴が首筋を伝い、くすぐったさに身を捩る。指先を動かして文字を綴ると、ふわりと金糸が舞い、風が残った水分を拭い去っていった。
触り心地のいい髪を指先に絡めていると、太腿に指先が伸びる。つ、と地肌を滑る感触に、思わず息を飲んだ。
「寝室いこ」
「宰相閣下と魔術師さんと再会の約束」サンプル
実家へ向かう馬車の中は、サーシ課長とシャクト隊長の会話する声だけが響いていた。俺がガウナーに話しかけたとしても、答える言葉は生返事が続いている。道中ずっと何らかの考えを巡らせているであろうことが分かって、俺も大人しく景色を眺めていた。
寒さに強い作物だけを選んで育てるとはいえ、これから冬に向かう畑は種を含んではいない。雪で覆われる大地では育てられる植物を扱う畑は極一部で、それ以外の畑は休みとなる。農業を営む家庭では、冬は別の仕事を持っている者も多い。
冬季の手工業は、季節に仕事を制限される民が選ぶことが多く、それらを金にするために付加価値を持たせるのも領主の仕事の一つだ。
雪が降る前の領地は、もうそろそろ作物の収穫も終えてしまう頃合いだ。
どこまでも土色が広がる大地は、華やかな王都と比べれば物寂しい。この地を盛り立てようとする父は、この光景に何を思い続けているのだろう。
ガウナーとの結婚は、言葉が纏まらずに手紙で報告をした。
急な話であったとはいえ、父も貴族の伝手で話を聞いていたのだろう。返事はガウナーの人柄を褒めるもので、手紙のお手本にするような文章だった。
父の不利になるような関係ではないが、この結婚が父の本心から喜ばしく思っているのか、薄い紙から読み取ることはできなかった。もっと別の相手との結婚を望まれていたかもしれないし、この結婚に自分の与り知らない難点があったかもしれない。
何より、家を出た息子が結婚することになんて、さほど関心を持っていないのかもしれない。
けれど、それを父に問うことはできなかった。
こつこつと指先で反対側の腕を叩き、頭に入らないまま領地を車窓から眺め続ける。
「そういえば、ロアくんの父君ってどんな人?」
「……うーん。本と魔術が好きで、同好の士と語らうのが好きなだけの、普通の人ですよ」
サーシ課長の言葉にそう返すと、普通? と俺の言葉は反復される。
「ロアくんと性格は似てる?」
「俺より物怖じしないのと、人を誘導することに長けている気がします」
隣にいるガウナーが、思考から起床して会話に混ざった。
「…………更に憂鬱になった」
「憂鬱だったんだ?」
腕を伸ばして頭をそっと撫でると、頼るように俺の肩に寄りかかった。どうやら、ナーキアでの騒動ではなく、俺の父と会うことに気を揉んでいたようだ。
青色の瞳は閉じられ、唸るような声が漏れる。
「手紙や通信魔術でやり取りしていても、頭が回る相手だということは分かる。直接会って話して、評価を落とされたらと思うとな……」
「確かに父さんは頭が回る方だけど、ガウナーも負けてないと思うし。兄弟はもう結婚していて、俺の結婚ってあんまり関心ないと思うけどな。ガウナー自身とは関係を持ちたい…………気がするけど」
「関心がなかったら、私に対してあんなに頻繁に手紙を送ったりはしないさ」
「そんなに来てた?」
尋ねると目を閉じたまま、こくりと頷いた。
「相当、探りを入れられている気がしたな」
とはいえ、俺に関心がなくとも宰相と伝手を持ちたかった可能性はある。そうかなあ、とその言葉を流しつつ、慰めるためにこちらからも身を寄せた。
サーシ課長はその会話に眉根を寄せるが、俺が気づくと表情を戻した。
「モーリッツの当主を普通、って言うのはロアくんくらいじゃない? 貴族の間でもそんなことを言う人はいないよ」
「ええ……。でも本と魔術が大好きですから、酒でも入れて放っておいたら何時間でも喋りますよ」
うわそっくり、と差し挟まれた言葉に、心外だと眉を顰める。
「その魔術が領地運営に紐付くのが強いよ。軍事では潤沢な魔術師がいて、商業や農業で使える魔術の改良が進んでいて、気軽に魔術師から授業が受けられる領地だもの」
それに、とサーシ課長は言葉を加えた。
「フィッカ領って、あまり資産を持たずに投資に注ぎ込んでいることを侮られがちだけど、モーリッツの一族間で資金や備蓄を融通すれば、一つの領地の資産は少なく済むんだよね」
「そうですね。作物の不作の年は必ず訪れますが、一族が各地に散っている所為で、どこかの領ではだいたい豊作の領地がありますから」
貴族間では敵対する関係性も多いが、親戚筋ということもあって、モーリッツ一族の仲は良好だ。父はどの領主とも仲が良く、遠出してまで顔を見に行く。手紙でいいのに、などとは、筆忠実な父に誰も言えはしない。
ガウナーにたくさん手紙が届いていた、と言われても、あの父ならさもありなん、だ。寧ろ、俺たちが向かうまで押し掛けてこなかったのは、ガウナーの顔を立てた形なのだろう。
馬車の床で眠っているニコが、ごろりと寝返りを打った。脚を放り出し、腹を見せることを躊躇わない姿は、何とも間抜けに見える。
「まあ、そんな有能な父君なのですから、息子が選んだ相手を無闇に反対することもないでしょう」
サーシ課長は、ガウナーに向けてそう言った。その言葉はガウナーの悩みに対しての助言であることは明らかで、俺はようやく伴侶の悩みの種を知ることになった。
「へ? ガウナー、そんな心配してたんだ?」
図星を突かれたように、ガウナーは視線を窓に投げる。
「父さん、ガウナーのこと好きだと思うよ。多分、色んな話をしようと構えてると思う。ナーキアの件で滞在日数が減ったのも残念がってそうだし」
「……ああ。もし反対されたとしても、もう君を離してはやれないしな」
手を覆うように重ねられ、とくりと胸が跳ねた。伝わる熱は少し冷たく、こちらの熱が伝わればいいと願う。
「うん。反対されたら、二人で逃げような」
ガウナーの口元が弧を描く。微笑み合う俺たちを余所に、向かい側でシャクト隊長が溜息をついた。
「この二人が共謀したら、完璧に失踪できそうなのが困る」
「違いない」
シャクト隊長の言葉に、サーシ課長も同意した。
馬車は広い道を走り抜け、襲撃を受けることなく実家まで到着した。近くに他の家がないため生け垣は低く、敷地内は遠くからでも見渡すことができる。
実家の領地は土地が有り余っているため、二人で使っているガウナーの屋敷よりも広々としており、客用の離れもある。
通路付近の庭園は人の手が多く入っているが、元々の土地の隆起を生かした区画や、池を崩さずに整えただけの区画もあり、庭園と一括りにするには多様な景色を持っていた。
見晴らしが良すぎる、という、防犯という観点からすれば悪い見本のような屋敷であるが、あの屋敷は魔術一族の本拠地である。ありとあらゆる防御用の魔術が実験される土地なのだ。いっそ、泥棒を誘って効果の検証でもしているのではないか、という節すらあった。
表の門の前に馬車を停めると、門の近くには使用人が既に待機している。馬車から降り、使用人達に馬車の誘導を任せていると、背後から優しく声が掛かった。
「おかえり、ロア」
やあ、と手を挙げているのは父であるイニアックだった。
俺に似た柔らかい暗褐色の髪は額から背後に撫で付けられており、華美ではないが、客人を出迎えるための質の良い服を身に纏っていた。
美形からは距離があるのだろうが、上品な所作も相俟って容姿は悪くなく、同年代に比べれば若々しい。目元はよく垂れて細められ、初対面の子ども達がすぐ抱きつくような、警戒心を抱かれづらい容姿をしている。
隣には母のレイリーが立っており、にこりと微笑みかけてきた。
母は北の出身で、髪の色は黒よりも灰に近い。母に関しては、王宮で美形を見慣れて尚、美しい容姿をした女性であると思う。俺自身は父似だと思うのだが、母は俺のことを自分にだって似ている、とよく主張する。
ガウナーから一歩退こうとした背が、手のひらに押されてその場に留められる。
「初めまして、というには手紙で話しすぎたかな。……イニアックだ。こちらは妻のレイリー」
「はじめまして。今日を楽しみにしておりましたわ」
まず父から差し出された手を、ガウナーが両手で固く握りしめる。あれだけ悩んでいた挨拶の言葉は一度吹き飛んだようで、伴侶の口は短く、そして心からの言葉を漏らす。
「……ガウナーです。こちらこそ、お会いできて嬉しい」
二人の手が離れると、父はその肩に腕を回してガウナーを引き寄せ、容赦なく背を叩いた。はは、と大きな口から笑い声が漏れている。
俺が二人を眺めていると、伴侶はその腕の中で背を丸めた。
「全く、今にも殺されそうなひどい顔だな。私からの言葉はこれだけだ、『おかえり、ガウナー』二人の息子が帰省するのを、今か今かと待っていたんだよ」
父の手のひらが丸まった背を撫でると、促されるように顔が上がった。先ほどまでの弱り切った声音ではなく、いつもの、屋敷での素の声だった。
「はい。……ただいま」
母も二人に歩み寄り、ガウナーの腕に手を添えた。新入りの家族はまだ照れくさそうで、二人にされるがままだ。
輪の外で眺めていると、父がこちらを見て軽く手招きする。
「……そうだ俺も。ただいま」
脚を踏み出してその中に入ると、ガウナーを構っていた腕がこちらにも伸びてくる。母は顔にできた掠り傷の上を、指で辿った。
「こんなに傷だらけになって。わんぱくなのはいいのだけど、時期を選びなさいね」
「式の前に傷じゃあ。仕立師が困るぞ」
ナーキアでの掠り傷に手のひらがそっと重ねられると、はぁい、とつい幼い返事が口から漏れる。珍しい服を着ていると父に誉められ、ガウナーに結われた髪を母は気に入ったようで、上機嫌だった。
一頻りわいわいやっていると、近くで執事が咳払いをした。
「ああ、済まなかった。後ろにいるのは、護衛の方だね?」
「シャクトと申します。王宮の防衛課に所属しております」
「サーシです」
二人とも手を差し出し、父はその手を両手で包み込んだ。貴族であるサーシ課長の両親とは面識があるようで、近況報告も交える。
「ナーキアでは息子達が世話になったね。精一杯もてなさせていただくよ」
足元でニコが、あぉん、と鳴いた。
自分も手伝った、とでも言いたげだ。父は不思議そうにするが、すぐに屈みこみ、両手でもふもふと毛を挟み始める。
「ああ。君が例の?」
ニコがきゅう、と何事か話しているが、通訳ができるルーカスは王宮に帰ってしまっている。だが父は、そうかい、と目じりを下げ、互いの頬を擦り合わせた。
ニコは伝わったのだ、と満足げで、何にも意思の疎通などできていないのに、二人とも揃って満面の笑みだ。
「そう、ニコっていうんだ。力が強くて、いい番犬になってくれてる」
父が手を差し出すと、はし、とニコは前脚を添えた。もう片方の手を差し出しと、ぱし、と勢いがつく。お手、と指示する前だというのに、何とも対応が早い。
「脚が太くて、身体もがっしりしているね。だが、犬にしては変わった種類だな……」
裏返した肉球の形や、目の中を覗き込み、父は首を傾げている。
俺は誤魔化し笑いを浮かべ、ニコを軽く手招きした。父の博識さには恐れ入るが、言い当てられても困るばかりだ。
父は立ち上がると、こちらへ、と屋敷に先導する。
滞在中はサーシ課長やシャクト隊長にも、離れの部屋が宛がわれるらしい。俺とガウナーに対しても、元々俺が暮らしていた部屋が狭いことを理由に、同じく離れを使うよう言われた。
屋敷の玄関から入らずニコが待っていると、使用人が湯で濡らした布を持ってきてくれる。自ら布の上に前脚を差し出す仕草は、笑いを誘った。
「昼食後は孤児院に行くんだったね? 子ども達に宰相の地位はぴんと来ないようだが、先生達はそわそわとしているそうだよ」
磨き上げられた廊下を歩きつつ、父がそう切り出した。
日程が短縮された影響で、俺たちが屋敷でのんびりする日数は削られたものの、予定の日取りで孤児院の視察に行けることになったのは幸運だった。
「視察を申し出たのはこちらですから、向こうに負担が少なければいいのですが」
「いいや。宰相から直接、授業を受けられるなんて願ってもない話だよ」
孤児院では少しの時間だけ、ガウナーが授業をする予定が組まれている。立っている者は親戚でも使え、が新しく増えた親族にも適用された形だ。
ガウナーも満更ではないようで、孤児院の先生宛に、年齢や普段の学習内容を尋ねる連絡を入れていた。
紙にやたら可愛らしい絵などを描いているものだから、何をしているのだろうと思っていたのだが、本人曰く板書の練習をしていたようだ。
「そういえば、兄さん達は?」
「ああ。ナーキアの件の収拾に、少し出ているんだ。明日か明後日には会えると言っていた」
本来であれば父が旅立っていた所だったのだろうが、宰相を招いておいて不在、という形にはできなかったようだ。
ごめん、とつい口に出すと、いいや、と父は言う。
「ロアが最前線に立ったことに思うところはあるが、領主としても、幼い孫を持つ身としても、今回は穏便に済んだと評価しているよ」
部屋の調度品を見れば、ずいぶん花瓶が減っていることに気づく。
落ちても割れないもの、落ちた先を傷付けないものが選ばれており、色味も鮮やかなものが増えた。兄弟たちが家族を連れてくるようになった屋敷は、また別の表情を持ち得たようだ。
俺は子ども達を助けたいとは思ったが、自身にとって彼らのような存在を身内に重ね、心を砕くには遠い部分もある。けれど、父は浚われた子ども達に、孫の表情を重ねるのだろう。
兄弟たちは地元に残り、父を支えて領地運営に携わっている。
俺はきっとこのまま王宮に勤め、老後は王都で暮らすことになるだろう。この領地の助けになるような経験を積めないまま。
視線はつい、部屋の隅を辿った。
「まあ、今回はこちらで下手を打っても、最終的には宰相閣下の助け船が期待できる。子ども達も、交渉ごとを学ぶいい機会になるだろう」
「お任せください。フィッカの防衛課を動かしていただいている分、こちらも働くつもりです」
ガウナーが胸に手を当て、そう約束する。
フィッカの防衛課を動かした対価として、兄弟達が交渉で失敗したとしても、ガウナーが自らの立場を使って補助をする。もし助けが要らなければ、別の対価を用意するだろう。
宰相との関係は、父が領地運営するにあたっては助けになる。
この関係は、俺あってこそなのは理解している。けれど、俺自身は家族の役に立たないまま、それが変わることはない。
昼食は温かい食事が用意されていたが、和気藹々とした空間は、すこし居心地が悪かった。


