 「お気に入り」へ追加
「お気に入り」へ追加
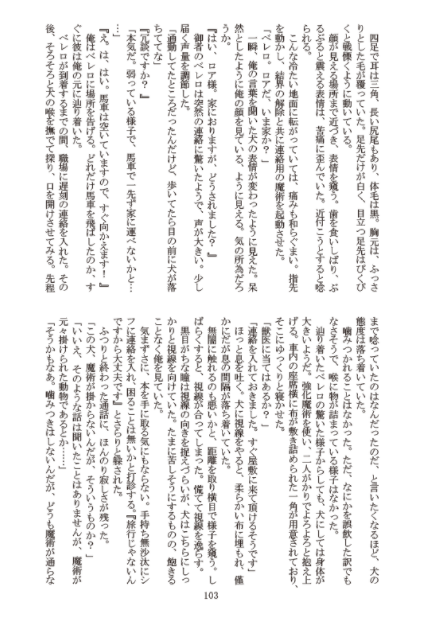
A5サイズ二段組124ページ
web再録
宰相閣下と結婚することになった魔術師さん ~国王襲撃事件編~:約10万字
書き下ろし
宰相閣下と魔術師さんと交わす睦言(本編直後):約0.4万字 ※18禁
宰相閣下と魔術師さんと星の犬(本編後):約2万字
※「宰相閣下と結婚することになった魔術師さん ~国王襲撃事件編~」はKADOKAWA刊、商業本にも収録されておりますので、ご注意ください
通販について
紙版→書店委託期間を終了しておりますが、定期的にとらのあなの取寄販売に登録しております、アナウンスはX(twitter)にて行います。
電子書籍版(BOOTH)→https://sakamichi31.booth.pm/items/1755958
※BOOSTは電子だとお礼のペーパー同封したりもできないので、基本的に支援のお気持ちだけで十分です。
頂いた分については普段の小説執筆のための事務品やソフト代、参考書籍代などに有難く使わせていただきます。
初版小説表紙のR18表記漏れについて
初版小説表紙にR18表記が漏れておりました。経緯や対応等の詳細はこの文をクリック
「宰相閣下と魔術師さんと星の犬」サンプル
その日は珍しく、宰相閣下は朝早くの出勤だった。
馬車への同乗を勧められたものの、朝食後の二度寝を狙って丁重にお断りする。
しょんぼりとした伴侶を撫でて宥め、行ってきますのキスという新婚っぽい行事をこなす。新婚を過ぎても伴侶なのだから、と結局なあなあにされそうなのが、伴侶の口の上手さの困る所だ。
二度寝をして執事のアカシャに起こされ、身支度をして屋敷を出る。ぶらぶらと歩く通勤経路は、数少ない一人の時間だ。
ただし、この通勤経路は俺一人しかいないため、王様や宰相閣下から良くは思われていない。あれだけ魔術式構築課をゴーレムで守っても、通勤経路の護衛が甘すぎるというのだ。
とはいえ、ゴーレムの稼働時間にも限りがある事だし、そのあたりは多くの人数を守れる時間に充ててもらう方がいいと、現在はこの状態で妥協している。
そんな俺の通勤経路は今日もいつも通り、堀の近くにいる野鳥を眺めつつゆったりと歩いていたが、遠目に奇妙な物体を目にして足を止める。
黒く明らかに大きな物体は、形状から明らかに生物であるようだ。そろりそろりと近寄りながら、軽く調査用の魔術を送る。
ぱしん、と魔術が弾かれた。
俺は思わず身構えるが、生物は呼吸の間に僅かに身体を動かすばかりで、襲う元気もないといった様子だった。
念の為結界を張り、いつでも逃げ出せるように転移魔術を準備しつつ足を進める。近寄って明らかになったその生物の形状は、犬に似ていた。
四足で耳は三角、長い尻尾もあり、体毛は黒。胸元は、ふっさりとした毛が覆っていた。足先だけが白く、目立つ足先はぴくぴくと戦慄くように動いている。
顔が見える場所まで近づき、表情を窺う。歯を食いしばり、ぶるぶると震える表情は、苦痛に歪んでいた。近付こうとすると唸られる。
こんな冷たい地面に転がっていては、痛みも和らぐまい。指先を動かし、結界の解除と共に連絡用の魔術を起動させた。
「ベレロ。ロアだ、いま家か? 」
一瞬、俺の言葉を聞いた犬の表情が変わったように見えた。呆然としたように俺の顔を見ている、ように見える。気の所為だろうか。
『はい、ロア様。家におりますが、どうされました? 』
御者のベレロは突然の連絡に驚いたようで、声が大きい。少し届く声量を調節した。
「通勤してたところだったんだけど、歩いてたら目の前に犬が落ちててな」
『冗談ですか? 』
「本気だ。弱っている様子で、馬車で一先ず家に運べないかと……」
『え。は、はい。馬車は空いていますので、すぐ向かえます! 』
俺はベレロに場所を告げる。どれだけ馬車を飛ばしたのか、すぐに彼は俺の元に辿り着いた。
べレロが到着するまでの間、職場に遅刻の連絡を入れた。その後、そろそろと犬の喉を撫でて探り、口を開けさせてみる。先程まで唸っていたのはなんだったのだ、と言いたくなるほど、犬の態度は落ち着いていた。
噛みつかれることはなかった。ただ、なにかを誤飲した訳でもなさそうで、喉に物が詰まっている様子はなかった。
辿り着いたベレロの驚いた様子からしても、犬にしては身体が大きいようだ。強化魔術を使い、二人がかりでよろよろと抱え上げる。車内の座席横に布が敷き詰められた一角が用意されており、そこにゆっくりと寝かせた。
「獣医に当てはあるか? 」
「連絡を入れておきました。すぐ屋敷に来て頂けるそうです」
ほっと息を吐く。犬に視線をやると、柔らかい布に埋もれ、僅かにだが息の間隔が落ち着いていた。
無闇に触れるのも悪いかと、距離を取り横目で様子を窺う。しばらくすると、視線が合ってしまった。慌てて視線を逸らす。
黒目がちな瞳は視線の向きを捉えづらいが、犬はこちらにしっかりと視線を向けていた。たまに苦しそうにするものの、飽きることなく俺を見ていた。
気まずさに、本を手に取る気にもならない。手持ち無沙汰にシフに連絡を入れ、困ることは無いかと打診する。『旅行じゃないんですから大丈夫です』とさらりと躱された。
ふつりと終わった通話に、ほんのり寂しさが残った。
「この犬、魔術が掛からないんだが、そういうものか? 」
「いいえ、そのような話は聞いたことはありませんが、魔術が元々掛けられた動物であるとか……」
「そうかもなあ。噛みつきはしないんだが、どうも魔術が通らなくて」
調査用の魔術が見事に弾かれ、原因を察することができない。全ての物事には原因がある。それを知ることができないのは、薄気味悪いものがあった。
犬に配慮しているのか、ベレロの走らせる馬車は普段よりも揺れが少なく、羽でも生えているかのようだった。すぐに屋敷に辿り着く。
待ち構えていた執事のアカシャに手伝って貰い、作られていた寝床に犬を運ぶ。
寝床は馬車内のそれよりも、ふかふかした毛布で作られていた。俺にはその毛布に見覚えがあった。普段、寝椅子で昼寝をする時に、俺が腹に掛けているものだ。
「ロア様には常々お昼寝用の毛布を買い直すようお伝えしておりましたが、毎回『まだ使える』と聞いては貰えず……、これ以上は言わずとも、お分かりですね? 」
「……分かりました。買い直します」
「はい。通いの商人に伝えておきましょう」
婿入り道具の安価なそれとは違い、商人に頼めば高級な品を持って来られるだろう。だが、アカシャが商人に頼む、と言うのなら支払いはガウナーの懐からだ。丁寧に耳掃除でもするか、肩でも揉んでやればいいだろうか。
一気に毛だらけになった愛用の毛布を見送りつつ、俺はそろりと犬に手を伸ばした。
噛みつく様子は無く、俺は身体中を探り、念のために怪我した箇所が無いことを確認する。
アカシャもベレロも気になるらしく、仕事が落ち着くと居間で待機を始めた。視線はずっと犬を向いている。
しばらくして、普段馬を診てくれている獣医が屋敷を訪れた。初老の獣医はまず犬の大きさに驚く。
「この大きさは、犬、でしょうか……? いいえ、犬のようですが、これほど大きな犬は見たことがありません。何の種でしょうね……? 」
「そう、ですよね。大きいとは思っていたんですが……」
俺が症状を伝えると、獣医はまず全身を目視で確認し、口内、と診察を続ける。いや、続けようとした。
ぱしん、と何かに弾かれるように、獣医の手のひらが犬から離れた。
「え? 」
獣医は目を白黒とさせ、再度手のひらを近づけようとする。その指先は、犬に触れる前に、空中の何もない場所で弾かれた。
犬は獣医に視線も向けず、畳んだ手に顔を乗せている。獣医は何度かそれを繰り返し、溜息をついた。
「魔術の実験用の動物とか、そういう存在かもしれません。見る限り怪我はないようですが、この状態で診察は難しい」
「でも、さっきは……」
指を伸ばすと、俺の指先は弾かれることなく毛皮に埋まった。獣医は目を見開き、首を傾げた。
「触れる人を選ぶようですね。口を開けていただくことはできますか? 」
俺はそろそろと犬の口を指で摘み、上下に開いた。犬は俺に嫌そうな視線を向けるが、されるがままだ。獣医は口内を観察し、異常はないだろうと言う。
その後も俺は獣医に言われるがまま、犬の体勢を変えては獣医の観察に協力した。
獣医は何事かを診療録に記入すると、鞄から栄養剤の瓶を取り出し、食事と共に与えるよう言った。
「嫌がられている……? ようでしっかり診ることが出来た訳ではありませんが、特定の部位が悪い訳ではなく、随分衰弱しているように見えます。栄養を与えつつ、しばらく様子を見ましょう」
獣医はまた数日後に様子を見に来る、異常があれば連絡を、と言い置いて帰って行った。俺は獣医を見送り、溜息と共に犬へと向き直る。アカシャもベレロも腕組みし、困った、という感情が露骨に顔に出ていた。
俺は栄養剤の瓶の蓋を取り、匂いを嗅ぐ。薬品らしい、およそ食物のそれとはかけ離れた臭いが鼻を突いた。人も飲みたがらないそれを犬に飲ませようとしたところで、素直に飲むかは怪しいところだ。
指に雫を数滴落とし、犬の口元に近づけてみる。犬はしばしその雫の付いた指を眺めていたが、ふい、と顔を逸らしてしまった。
「だよなあ。俺も飲みたくない」
「ロア様がそう言っては、犬はもっと飲もうとしませんよ」
アカシャに布巾を差し出され、有難く指先を拭う。うーん、と口から意味を成さない声が漏れた。
「食べ物のことは詳しくないけど、水くらいは飲めるよな? 」
「持ってきましょう。ロア様はゆっくりしていてください」
底の深い皿に水を注ぎ、アカシャは犬の前にそれを置いた。犬は皿に視線をやり、そわそわと期待して待っている三人に視線をやり、そろりと皿に舌を伸ばした。ぴちゃぴちゃと水面を舌が叩く音が響く。
「飲んだー! 良かった」
気が済むまで水を飲み、俺の様子を眺めて、犬はまた身体を丸めた。
「あとは食事……消化に良いものを用意しなければいけませんね」
料理長のイワに相談してみる、とアカシャが言うので、全て任せることに決め、俺はほう、と息を吐く。朝っぱらからどたばたしていたが、ようやく落ち着いた心地だ。
そうだ、と丁度落ち着いたのをいいことに、ガウナーに連絡を入れる。
「ガウナー、いま連絡しても平気か? 」
間髪入れずに返事があった。
『ああ、君からの連絡を待ちわびていたところだ』
俺が意図を掴めずにいると、ガウナーは言葉を重ねる。
『さっき廊下で君の部下……フナトに会ったんだ。犬は大丈夫かと尋ねられたが、全く私の元には伴侶から連絡が来ていなくてな。全く。何にも。一言も』
俺はしばし無言になり、心から通話を切りたくなった。ガウナーは怒っているわけではなさそうだったが、声音から拗ねているのは分かる。ただ、まず謝罪よりも、端的に経緯を説明することを優先した。
「あの……、勝手に、朝に通勤途中で倒れてる犬を拾った」
『遅い報告だったな』
「はは……みんな動揺しててさ。さっき水は飲んでくれた。弱っているようで、イワに頼んで消化しやすいものを作ってもらおうと思ってる」
『すぐに死ぬような容態でなくて良かった。どんな犬なんだ? 』
「全体的に黒くて、足の先だけ白いんだ。身体は大きくて……」
ガウナーに犬の外見を伝え終えて一息つくと、話題にされていた当の本人がこちらをじっと見ていた。
俺がなに? と顔を向けて首を傾げると、視線が逸らされた。
『人懐っこいのか? 』
「いいや全く。魔法は弾かれるし、獣医の手も弾くしで、何かの魔術の実験動物かもって話したとこ」
『……。犬とはいえ、警戒はしてくれ。今日は早く帰るよう努力する。まったく、君が来てから屋敷が騒がしいな』
勝手に犬を拾ってきて、悪いことをしただろうかと俺が口を噤むと、ガウナーは言葉を重ねた。
『だが、君がいない屋敷は、もう家だとは思えないだろう。そのまま賑やかにしていてくれ』
「自分だけで決めてごめんな。犬がいるなら別居って言われたら、……考える」
『飼い主が見つかるかもしれないし、犬に会ってみないと何とも言えないが、元気になる前に追い出すなどしないとも。あと、そこは君の家だ。ロア』
一拍遅れてそうだな、と同意すると、ガウナーは満足そうにそうだとも、と返事をした。
勝手なことをしたとしても、追い出されることは無いらしい。良かったな、と近づいて犬を撫でると、その指が耳の裏に当たるよう誘導された。
痒いのだろうか、と導かれた箇所の皮膚を掻き、毛を梳く。
「あ、ごめん。連絡が長くなった。今日は犬が心配だし、休みにしようかと思ってる。屋敷で、帰ってくるのを待ってるな」
『帰って、ゆっくり話を聞かないとな。またな、ロア』
最後に宰相閣下は、悪戯っぽく言葉を付け足す。
『愛しているよ。突発的な休日だが、犬の様子見はアカシャに任せて、たまにはゆっくり休むといい』
ぱくぱくと口を開閉させ、両手で顔を覆う。
「…………おれも」
『ん? 』
「俺も、愛して、ま、すよ」
にやにやとしているアカシャとベレロの姿が目に入る。しっしっと手で追い払い、ぐああ、と羞恥に頭を抱える。
『その言葉も、帰ったらゆっくり聞かせてくれ』
はいはい分かった、と名残惜しそうなガウナーとの通話を打ち切る。
何だったのだろう今の時間は、とぐったりと疲れ果て、眼鏡を持ち上げて寝椅子に転がる。犬が落ちていたとはいえ、休み自体は有難い。犬の様子を見つつ昼寝をして、部屋の隅に積んでいた本を読んで過ごそう。
イワが作った料理を、犬はまた俺達の視線を気にしつつ腹に収め、匙で差し出した薬を仕方なさそうに舐める。
あんまりな味だったのか、飲み終わった後しゅんと悄気返り、様子を眺めていた四人ともがつい笑ってしまった。
ガウナーが帰宅した頃には、ただ遊び疲れている犬、のように見えるほど落ち着いていた。俺がガウナーを出迎え、一頻り抱擁されている間も、眠ることなく新しい人物の登場を見守っている。
「おかえり。有言実行でかっこいいなー、宰相閣下」
広い背中を抱き返すと、耳元でくすくすと笑い声が響いた。
「ただいま。宰相補佐のおかげかな」
とはいえ、簡単なことでもないだろう、とぎゅう、と抱きしめる腕に力を込める。キスをどうぞ、とばかりに頬を向けて目を閉じるものだから、大人しく眼鏡を外し、顔を寄せる。
恥ずかしい、と口付けした後で胸元に顔を埋めていると、指先で寝乱れた髪を整えられる。
「ん? 」
ガウナーの声に視線の先を見ると、足下にもふりとした感触が纏わり付いた。起き上がった犬が寄ってきていたのだ。
伴侶の帰宅に夢中になっていたためだろうが、気配が薄かった。犬は鼻先をガウナーの足元に近付け、服の匂いを嗅ぐ。
身体を離すと、ガウナーはしゃがみ込み、犬と視線を合わせた。鼻先は全身をくまなく辿った。気が済むまでそうすると、何かを言いたげに声を上げ、前脚で服を掻く。
「……美味そうな匂いでもするとか? 今日、何かあったか? 」
「いつも通りだ。王宮でスクナを含めて頭の固い大臣達との会議と、神殿でルーカスや神官達との会議と、サウレと個人的に打ち合わせたくらいで、珍しい人と会ったりもしなかったんだが……」
心当たりはなさそうで、宰相閣下は考え込むが、やがて首を振った。眉を下げ、犬の頭に手を伸ばし、ひと撫でする。
「すまない。何かを伝えたいんだろうが、心当たりがなくてな」
犬はそれからも何かを伝えようと、ガウナーの周囲をうろうろとしては前脚でつついていたが、やがて諦めたようだ。あからさまに気落ちした様子で、のそのそと俺のお昼寝用の毛布へ帰って行った。しょんぼりと毛布を口で引き寄せ、居心地良く形を整えている様を見ると、毛布を取り返す気にもならない。
俺はガウナーと視線を合わせると、互いに首を傾げた。
「あれは……、本当に、実験動物とでも言われた方が納得するな。ある程度の思考があり、こちらの言葉も汲み取られているように感じる」
「そうなんだよ。食事も、薬も、こっちが飲んでくれないと困る、って言ってるから飲んでくれてるように感じて」
まあ、食事がてら話そう、と食卓に向かい、イワが先ほど作り上げたばかりの食事を並べる。普段は宰相閣下が遅いため、冷めてしまうのだが、今日は全体的にまだ温かいものばかりだった。
アカシャもベレロもイワも、犬の様子が気になる、と残ろうとしていたが、二人いるから大丈夫、と三人とも今日は帰している。昼間は大人四人がべったりと張り付いていたが、容態が悪化するようなことはなく、立ち上がり、歩く姿からも骨などに異常はなさそうだった。
向かい合って席に座り、手を合わせる。野菜を煮込んだスープに匙を突っ込み、くるくるとかき混ぜた。
「頭がいいというか、人間味溢れすぎてる、っていうか、水も薬も素直に飲む。ただ、薬は嫌いみたいで、イヤ、って主張して、でもちゃんと飲んだ後、拗ねて寝る」
ガウナーは、ちらりと犬を視界に入れる。
「確かに、犬にしては大きい。ただ、私は手は弾かれなかったな」
「ああ、確かに」
獣医は容赦なく手を弾かれていた。出会ったばかりだったからかもしれないが、初対面ならガウナーも同じだった。そういえば、俺がガウナーと通話している間も、犬は反応を示していたのを思い出す。
白身魚の身を切り分けつつ、ガウナーは口を開いた。
「ちなみに、アカシャやイワ、ベレロはどうだった? 」
「ベレロは最初の方から弾かれてなくて、アカシャもイワも帰り際には触れるようになってたよ」
何となくだが、世話になった人物というものを認識しているように感じるのだ。イワは料理を渡したことで、アカシャは親切に世話をしたことで、犬は彼らを触れてもいい人物だと認識したのかもしれない。
だが、それならガウナーは出会ったばかりの人物で、弾かれる対象のはずなのだ。
「魔術はどうだ? 」
「魔術は今も全然効かないな」
スープに浮いている芋を、割ろうと底に押し付ける。力の加え方が良くないのか、芋はなかなか割れることはなかった。諦め、掬い上げて歯で囓る。
「本当に分からない。魔術式が彫られている訳でもない、魔術の痕跡も全く感じない。けど魔術が通らない」
「君がお手上げ、というのは珍しいな」
「本当だよ! 」
スプーンを握り締めた俺に、ガウナーは微笑した。
「魔術を弾くっていう挙動には、魔術が伴う。だから分かるはずなのに、全く分からない」
むむ、と眉間に皺を寄せて芋を潰す作業を繰り返す俺を、ガウナーを目尻を下げて見ていた。
実験動物なら埋め込まれている魔術式があるはずだ。考えられる魔術の組み合わせを浚っているのだが、全く条件に合致するものが見つからない。難問とはいえ、解けないというのは魔術式構築に携わる者としての沽券に関わる。
「そうだな。本当に、魔術を弾けるのは魔術だけなのか、と私は思う」
彼はぱくり、とソースを絡めた白身魚を口に入れる。
「火を消すのは、魔術だけではない。土を被せてもいい、君の課のエウテルがやったように、空気を変質させてもいい。ならば、魔術が弾かれる、という現象についても、魔術以外にも手段はあるだろう」
「そっか……、成程。もう少し魔術以外でも考えてみる」
ようやくスープを口に入れたが、咀嚼の必要がないほど芋は滑らかに混ざっていた。
それからは、今日一日を早く終わらせるための顛末を聞くことに終始した。会議を長引かせないこと、持ち帰りの仕事を作らないために宰相補佐のスクナが珍しく強く発言したくだりには、思わず息を漏らした。
食事を終え、食器を片付けながらガウナーに問う。
「今日、寝る時どうしようか」
思わず視線が、僅かに犬の方を向いてしまう。俺の思考は読まれていたらしく、頷き返された。
「犬の声が届く位置で寝てもいいが、寝室に来てくれると助かるな。呼んだら伝わるだろうか? 」
ガウナーは歩いて行くと、犬の傍にしゃがみ込み、「具合が急に悪くなるのが心配だから、自分たちの寝床の傍で寝てくれないか」と語りかけた。まさかそんな、と俺が食器を置きつつ視線をやると、犬はゆっくりと立ち上がり、毛布の裾を咥えた。
ガウナーは犬の意図を察したのか、毛布を丸め、噛んでいる裾を引いた。犬は素直に毛布を口から離す。
「こちらだ」
毛布を抱えてゆっくりと先導する背を、同じ速度で黒い毛玉が追って行く。俺は呆然とその様を見送った。
嘘だろ、と声を漏らし、早足で追い掛ける。階段を苦にする様子もなく、犬は寝室まで辿り着いた。寝室をすんすんと嗅ぎ回り、寝台の横、部屋の隅で立ち止まる。
「ここか」
ガウナーが毛布を下ろすと、犬は礼を言うように、その手に頭を押し付けていた。犬はその毛布を先ほどまでと同じように、几帳面に丸めて寝床として整える。寝床が出来上がると、その中心で足踏みをし、身体を横たえた。
「ロア。口が開きっぱなしだぞ」
「いや、何だ? これは」
「まだ偶然かもしれないが、意思疎通が出来ているのだろうな……。素直でいい子じゃないか」
ガウナーが頭を撫でるのを犬は受け入れているが、やはり耳の後ろを掻いてほしいようで、指先をそちらに誘導していた。そうか、と律儀な屋敷の主人に掻いて貰っている瞳は、とろりと細められている。
「ガウナーの方が、懐かれていてずるい」
「はは。逆に私は、君にたくさん撫でて貰う方が嬉しいがな」
う、あ、と口を噤んだ俺は、風呂の準備、とその場から離れる。俺の背を追うように、低い笑い声が廊下に響いた。


