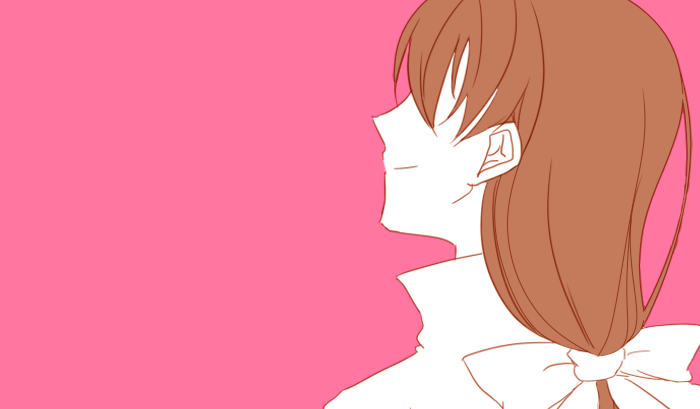「お気に入り」へ追加
「お気に入り」へ追加
※R18描写あり※
18歳未満、高校生以下の方はこのページを閲覧せず移動してください。
性描写が存在するキャラクターは全て成人済みです。
作品は攻め視点です。
元々、肩も腰も悪かった。
王宮での書記官という仕事は、延々と手を動かしては文を作り、書き写すのが仕事である。一日中、文字と睨めっこをしている仕事柄、椅子に座りっぱなしで一日が終わることもままある。
王宮内のお使いという用事が発生すると、部内で届ける書類を奪い合うのが常だった。みな四本脚に縛られ続ければ、流石に二本脚で歩きたがる。
目、肩、腰の不調は職業病と言って差し支えなく、仕事が楽になる度に通院を繰り返していた。
けれど、この時期の仕事は凄まじく、体調が悪化し、仕事がぎりぎり落ち着いた途端に職場で気絶した。
忙しさも勿論だったが、ここ最近は更に体調が酷かったのだ。
立っているだけで体力を吸われているようで、大量に物を食べてもすぐに腹が減る。好んで作っていた料理も、すぐに腹に消えてしまうため億劫になった。
当初は暴食する俺を笑って見ていた同僚達も、食べても食べても太らずに腹を減らしている俺を見て、流石に通院を勧めてきた程だ。
倒れて医務室に運ばれた俺は、当然のように病院行きとなった。診察を受けたところ、症状は栄養失調らしい。
「きちんと食事は取っていたのですが」
「うーん。ただ、典型的な栄養失調の症状でねえ……」
医者に食事内容の変化を述べたのだが、老医師は首を傾げるだけで、まず栄養剤で様子をみることになった。
職場からは良い機会だと一ヶ月分の休暇の消化を命じられ、仕事を片づける間もなく休暇に入る。
ただ、休暇が始まるとそれらの栄養剤は効果を発揮し始め、栄養剤を飲んでいれば普通より食べるくらいで生活を送れるようになった。あとは体力を使わないよう心がけていれば、休日を寝て過ごすことは容易い。
ただ、困ったのは何かをやろうとした時だ。
散らかった部屋を片付けようと身体を動かせば、栄養剤を飲んでいたとしてもすぐに疲れて腹が減った。このままでは職場に復帰したとしても、また倒れる羽目になる。
「医者を変えるべきか」
診察に若干の不安を感じたが、まず身体を休めなければ完治も見込めない。時計を使わずに過ごし、身体が動かせそうならば散歩をした。
その日は、眠りすぎて昼過ぎに目が覚めてしまった。
食事を用意するのも億劫で、布団の中で微睡んで過ごす。しばらくすると日も暮れ、流石に食事をせねばと買い置きを漁ったが、これといって食べたいものが見当たらない。
散歩がてら酒場で夕食をとるか、と腹をさすって、着替えを始めた。
灰色の髪と、髪色を少し濃くした色の瞳。色の悪い顔はやつれ、目の下には隈の名残があった。代わり映えのない、色合いも地味な服を身に纏って家を出る。髪も目も地味な色の所為で、服の色を質素に纏めると、もう少し考えろ、と言われがちだ。
橙から紫へと移り変わる町は、ぽつぽつと灯りが点きはじめていた。
歩を進めていると、どんどん腹が減ってくる。仕事帰りらしい人々の波が、肩を掠めては流れていった。彼らを見送って、妬ましく向けた視線を道に戻す。体調が元に戻らなければ、俺はあの波には戻れない。
馴染みの酒場の扉を開けると、人は疎らだった。
店主に挨拶をして、隅のテーブルに腰掛ける。お品書きから食事をいくらか選んで、酒も頼まなければ悪いだろう、と一杯だけ注文した。
俺の後から、一人の青年が店に入ってくる。青年は、店に入るなり中を見渡している。その様子を眺めていると、視線が合った。
ぱあ、と青年の表情が明るくなり、店主に挨拶をしてから大股で店内を横切る。青年は俺の座ったテーブルの前に立った。
「こんばんは、お兄さん。少しお話ししたいことがあるんだけど、座っていい?」
「……詐欺か?」
「いや? 本当にお話がしたいだけ、物も売らないし美人を紹介したりもしないよ」
店主の視線も気になり、どうぞ、と手のひらを向ける。
青年はにんまりと笑って、向かいに腰掛けた。お品書きにさっと目を通すと、何を頼んだか俺に確認し、品物が被らないように料理と酒を注文した。
「勿論、食べた分は払うよ。……そうだ、はじめまして。リジェっていいます」
髪は肩あたりで括られ、毛先は背の真ん中ほどにまで届いている。
目元はくりくりとして愛嬌があり、吊り目がちだが何処か愛らしさを覚える容姿だった。美形というより、特定の嗜好を持った人間に偏執的に愛されそうな人種だ。
目の色は鮮やかで、色味のない自分からは羨ましく思える。
「ヴァレリーだ」
名前だけを告げる。
付け加える言葉があるか思案したが、何も思いつかなかった。堅物だの面白みがないだの言われがちだが、きっとこういう所なのだろう。
「じゃあ、ヴァレリー。お仕事は何してる?」
「……文なんかを書くことが多い」
「ああ、手の平にも硬いとこあるなあ」
王宮の書記官だという詳細まで、素性の知らない人間に伝える気にはならなかった。リジェと名乗った人物も、そっかぁ、と立場を突っ込んで聞く様子はない。
その代わり、ずっと椅子に座って過ごすのかと問われ、頷き返した。詳しく、と促された答え……朝から夜までの行動という俺のつまらない話を聞くリジェは楽しげで、細かく相槌を打ってくれる。
「何でそんなにげっそりしてるの? 肌もがさがさ。ちゃんと食べてる?」
「食べてはいるんだが……」
言葉を続ける前に、店主が食事と酒を運んできた。
リジェは手元に俺の分の酒を引き寄せると、まず一番軽い食事の皿を押し出してきた。促されるように、食事に手を付ける。
一口食べると食欲が込み上げてきて、二口、三口と続けて口に含む。一段落するまで、俺はがつがつと食事を貪り、その間、目の前の存在を忘れていた。
はっと我に返り目の前に視線を戻すと、リジェが指先を組んで俺を見つめていた。その表情は先ほどまでのにこやかなそれではなく、じい、と真剣に見入るような視線だった。
「何というか。よく、腹が減ってな」
「へぇ……、その割には細いけど、生まれつき?」
「疲れて腹が減るようになった。最近のことだ」
リジェは自分の方にも料理を取り分け、食事を始めた。
綺麗な所作ではあったが、俺に負けず劣らず食事が速く、吸い込まれるように口に消えていく。邪魔なのか耳元に髪を掻き上げるのだが、指先がほっそりして生白く、その仕草に視線が吸い寄せられた。
リジェは俺が頼んだ酒を自分で飲み始め、俺が視線で追うと、自分が頼んだ方の酒を差し出してきた。受け取って口に含むと、ずいぶん軽い酒だった。
「最近、……変わったことあった?」
「忙しかった」
「あー、そりゃ食事量も増える」
忙しかったから仕方ない、というような症状ではないのだが、それを目の前の青年に訴えるのも気が引けた。
お互いに料理の感想を述べながら、食事を続ける。酒を控えている俺とは違って、リジェは無茶と思えるほど杯を重ねていた。
「リジェの仕事は?」
俺が問い掛けると、リジェはきょとんとした顔をした。
自身に話を振られることを予期していなかったらしい。ぱち、ぱち、と瞬く目は見開かれており、俺がリジェの話を促したことを意外だ、とでも思っているようだった。
麺を巻きながら、リジェは答える。
「お話をすることかな。でも、ヴァレリーとこうやって話してるのは仕事じゃないよ」
「ほう。じゃあ何だと言うんだ」
「求愛」
ごふ、と酒をグラスに噴き戻した。
立ち上がったリジェがハンカチを頬に当て、飛び散った酒を拭ってくれる。悪い、と声に出しながらも、自分が悪いのだろうか、と自問した。
ごほん、ごほんと咳払いし、呼吸を立て直す。
「悪い。聞こえづらくて」
「一目惚れしたから、こうやってお話したかったんだよね」
聞き直した言葉もまた、言葉が間違っていなかったことを示していた。
リジェに目を向けると、ばちりと視線が噛み合った。視線は逸らされることなく、意志の強そうな瞳がこちらを絡め取る。
彼の言葉は信じ難かった。俺は美形と言われるような顔立ちではなく、一目惚れされた経験もない。
「……俺は、男女共に恋愛は苦手だ。悪いが、冗談だったとしても判断できん」
「別に冗談じゃないけど。まあいいや、冗談かどうかは喋っていれば分かるよ」
次々と料理が届き、その度に二人で平らげていく。
リジェは酒も進んだが、俺は強い酒を飲ませては貰えなかった。果実酒を飲みながら、美味い料理で腹を満たしていく。二人で四人前以上を食べきった後で、ようやく落ち着いた。
ほろ酔いといった俺とは違って、リジェの顔は赤く、酔いが回っていることが窺える。唇がくっきりと浮き上がるように色づいていた。
「お腹が空くなら、甘い物もいいよ」
そう言って、氷菓子を二人分頼んでつつく。僕のも食べなよ、と勧められるものだから、半分残ったリジェの菓子は俺の腹に収まった。
薄くなった酒を腹に流し込んでいると、リジェが口を開く。
「この後、僕の家で飲み直さない?」
「やっぱり詐欺か何かじゃなかろうな……」
「そんなに疑うんなら、ヴァレリーの家にするよ?」
お金だって出すし、と今日の飲み代として紙幣をテーブルに載せる。飲み代の半分よりはおそらく多いだろう金を見れば、飲食代をたかるつもりもなかったようだ。自分も財布から金を出し、紙幣のうち数枚をリジェに押し返した。
「それじゃあ、ヴァレリーの分が多くなるよ」
「多く食べているから当然だ」
紙幣を持って店主の元に向かい、支払いを済ませる。残った酒を最後まで飲み干したリジェは、俺の後を追ってきた。
店主から釣りとして渡された小銭を、リジェの手に握らせる。だが、財布を取り出すのは面倒だったようで、いらない、と言いながら雑に懐に仕舞わされた。
多く払ったのを気遣われたらしい、更にこの青年のことが分からなくなった。
店の外は寒さが厳しく、リジェもまた寒い、と言いながら俺に寄り添ってきた。逃げようとすると、腕を組まれる。
「ヴァレリーの家で飲み直すんだからね」
決定事項のように言うリジェは、俺の家でも構わないらしい。周囲を見渡してみるのだが、追ってくる影もなかった。美人局か、とも疑ったが、そういう訳でもないようだ。
本当に飲み直したいだけのリジェを振り切れないまま歩いていると、すぐに自宅に辿り着いた。酒は買い置きがあったし、酒のつまみくらい用意はできるだろう。
手を洗いたい、と言うので水場に案内し、その後でテーブルの上に酒瓶を並べる。好きに飲んでいい、と言うと、歓声が上がった。
俺からグラスを受け取り、最も高い酒を容赦なく注いでいる。
「飲み過ぎたら金を取るぞ」
「手持ちで足りなかったら、身体で払うよ」
「要らん」
手早くつまみを作って皿に載せ、リジェの前に差し出す。
注いだ酒を呷る喉は白く、噛み付く牙を誘っていた。並べた酒の中でどれを飲もうか思案していると、やはり度数の低い酒をリジェから押し出される。
大人しくその酒をグラスに注いだ。
「氷いる?」
「いや、買ってはいないが」
「ある? じゃなくて必要かどうかを聞いてるんだよ」
「あったらな、というくらいで、買いに行かなくてもいい」
リジェは立ち上がると、水を出して、と言った。
促されるままに器に水を注ぐと、細い指先が宙を舞った。指の軌跡は光を纏い、空中に文字を綴っていく。重なる文字は揺れ動きながら、おそらく規則性を持っているであろう言葉をその場に生み出す。
「起動」
ぱん、と両手が打ち鳴らされると、水を湛えた容器からピシリ、ピシリと音がした。表面は音を立てながら白み、ぬるかったはずの水が、自ら冷気を漂い始める。
こういった芸当のできる人間を、王宮勤めの俺はよく知っていた。
「魔術師……だったのか」
「まあ、腕はそこそこだけどね」
リジェが触れると、器から出した氷はぱきぱきと崩れ、酒に放り込むのに丁度いい大きさになった。ぽんぽんと酒に氷を放り込まれると、グラスは冷たく結露を纏う。
腕はそこそこ、と言われても、俺に魔術師の腕を判定するための予備知識はない。学べば理屈が分かる学問とは違って、魔術という分野は自身が体験できない分、遠い分野に思えて仕方がなかった。それが苦手意識に繋がり、魔術方面には無知に等しい。
リジェは自分のグラスにも氷を入れ、機嫌良く飲み始めた。俺の出したつまみを、指先を使って口に放り込む。
「美味しい! 料理得意なんだ?」
「趣味程度にな。疲れている時は作らない」
「へえ、僕は食べる方が好きだよ」
聞いてもいないのに自分のことを語るリジェは、俺が問い返すことなどしないと決めてかかっているようだった。
俺がリジェに興味など持たない、と最初から期待することもない行動が、張った線を揺らした。
「何が好きなんだ?」
そう尋ねた時、僅かに目が見開かれた。ゆっくりと瞬きする動作を、静かに観察する。
「……んー。何が好き、もあるけど、品数が多いのが好きなんだよね。一皿に、お肉と野菜と、ごはんが盛られてるやつ。と、お酒と、甘いものも」
もしも今日、彼が泊まっていくのなら、明日の朝には料理の腕を振るう機会もあるかもしれない。
酒が脳を甘く溶かして、見知らぬ他人を懐に放り込んでいく。リジェに対する警戒心は消え失せ、泊まっていくのなら、と仮定している自分が何処かにいた。
「それは……、俺も好きだな」
話の途中で、書記官だということはおおよそ伝わるであろうくらい、取り留めのない話をした。家を出たのは夕方頃であったはずだが、二人でちびちびとやっていると、あっという間に真夜中と呼べる時間になる。
リジェの目も眠気に瞼の境界を作り始め、翠玉の瞳が隠れていく。
「今日はどうする?」
言葉を切って、放とうとした言葉に驚いた。
ああ、自分は酔っているのだ。
「朝まで、寝ていくか?」
「………………」
リジェの両手の間から、滑り落ちたグラスの底がテーブルを叩いた。ぽかんと口を開けた姿は間が抜けていて、初対面の時に感じた愛嬌が増して見える。
「……へえ、そんなに身体で払ってほしいんだ?」
続けられた言葉も、負け惜しみのように聞こえた。
どうせそんなことは出来ないだろう、と高を括った様子に、駆り立てられるものがある。この青年は、それを分かっているのだろうか。
「そこまで言うんなら、払ってもらおうか」
互いに互いを挑発して、後には引けなくなっている。
一瞬、リジェが唇を噛み締めた。
がたりと立ち上がると、指先に光が灯る。酔って拙い筆跡は空中を漂い、それでも何事かに収束して、爆ぜて消えた。
リジェの頬は真っ赤に染まり、俺の服の裾を掴む。
「来なよ。勃たなかったら一発殴らせて」
夕方に抜け出たばかりの寝台は、布団も雑に放られていた。
ぼすん、と荒く腰掛けると、リジェは髪の結い紐に手を掛ける。結われていたそれが解けていくと、少し大人びて見えた。
自分の居場所に迷っていると、手を掴まれて寝台に招かれた。自身の寝台であるはずなのに、別の場所のような気さえする。
両肩に手が添えられ、整った鼻先が近づいてくる。こつん、と額がぶつかると、促されるように瞳を閉じた。
柔らかい唇が触れ、ややあって離れる。
「恋愛は苦手なんだっけ。くち、開けるから舌ちょうだい」
膝立ちになり、上から被さってくるリジェを受け止め、唇を重ねる。僅かに開いた唇から舌を滑り込ませると、少し小さな舌が絡むように触れた。
口内を辿ると、柔らかく受け止められる。
「…………ふ、ぁ……」
唇の内側をなぞり、舌裏を擽る。上擦った声が漏れるのが心地よく、夢中になって貪った。混ざった唾液が口の端から溢れ、ようやくお互いの口が離れる。
舌を伸ばして口の端を舐め取ると、赤らんだ目元がこちらを見ていた。
「もっと、触って」
掃除もろくにできないほど力が入らなかったというのに、腹が満たされている所為か、この青年を組み敷きたいという欲が湧き上がる。上着の裾を持ち上げる指と入れ替わるように、腹に手のひらを差し込んだ。
上がった体温と、薄く肉がついた腹。指先を伝わせると、骨の位置がすぐに分かった。白い首筋に誘われるように唇を当てる。
「ヴァレリー。僕、まだ胸は感じないと思うからさ。下、触りあいっこしよう」
下の服を脱ぎ捨てたリジェは、寝台に乗り、腰から太腿の間まで下着を引き下ろす。俺が股の間に視線を向けていると、見せつけるようにゆったりと脱ぎ落とした。
彼を追って寝台へ上がると、指先は俺の服にも伸び、ベルトを外して前を寛げる。自分とは違う細い指先が下着の中に潜り込むと、男根が持ち上げられた。
躊躇いのないその仕草に慣れを感じて、不愉快な気分になった。
「……俺は何人目の男だ?」
「やだなあ。一人目だよ」
躊躇いのない返答に、真実味は感じられなかった。
青年の太腿に指を伸ばすと、目の前の唇が愉しげに弧を描く。日の下に晒されない部分は、薄明りの中で白く灯っていた。滑らかなその部分に指を食い込ませれば、むっちりと受け止められる。
服の下に隠れた中心に手を伸ばすと、小ぶりなそれが大人しく掌に収まった。
「触りやすい大きさをしているな」
「可愛がりやすくていいでしょ。ヴァレリーくらいあるのも好きだよ」
両手を使って握られ、ゆったりと扱き始める。
酒で上がった体温は熱く、他人の指で快楽を得ているのが物慣れない。普段と違う場所が擦られるが、その触れられた箇所は悪くない心地がした。
動きの間隔を追うように、慎重に他人のそれを擦る。
「……ん、ふ。先っぽ触るの、いい、よねぇ…………。いたくない?」
「丁度、いい」
丸く整えられた爪の先が、鈴口をやわく掠めていく。
白い指が裏筋を伝い、先端を優しく弄る様子が、視覚からも疼くものを起こさせる。褐色の髪は薄明りに彩を落とすが、その頭は傾ぎ、俺の肉根に視線を落としている。
「あまり見るな」
「へへ。舐めたいなぁ、って思って」
「…………いずれ、な」
膝を使って近寄ってきた細い肢体が、肩に寄り掛かった。
俺の胸元に指先が這い、小さい舌が首筋をぺろりと舐める。猫がじゃれつくような仕草だ。くすぐったさに身を引こうと思ったが、自身を人質に取られている状況に思い留まる。
「指、貸してくれる?」
ここ、と導かれた先は、白い双丘だった。
男はそこを使うのは知っていたが、ざっくりとした知識ではある。鷲掴むように指を埋めると、水分を含んだ肌は弾み返した。
もちもちとした感触を楽しんでいると、もう、と横から焦れた声がする。
「違うって。指を挿れて、準備してほしいんだってば」
かぷりと肩に噛み付かれ、未経験の無知さを指摘される。甘噛みとして歯を立てられても、攻撃されている感じがしない所為か心地いいくらいだ。
「……こう、滑りを良くしたりしなくていいのか」
「あ、そっか」
ぽそり、ぽそりと何事かが囁かれると、寝台の上に鞄がぽんと落ちる。それはリジェが使っていた鞄に違いなかった。彼は慣れた動作で鞄を漁ると、円柱形の瓶に入ったものを取り出す。
くるくると蓋を外し、瓶だけをこちらに差し出した。
「保湿剤だから、これ使って」
指先を瓶に突っ込み、粘性のある液体を掬い上げる。瓶を返すと、リジェは軽く蓋をしてシーツの上に放った。そして膝立ちに戻り、肩に掴まってくる。
尻の谷間に指を這わせ、窪みに指を挿し入れる。つぷり、と抵抗なく指先が埋まった。襞を掻き分けるように二本目を添え、纏めて押し込む。
「ひゃ…………、わ、……っ、うぁ」
上擦った声と共に、肉輪がぎゅう、と指を引き絞る。その波をやり過ごし、ぬめりを借りて奥へ潜り込む。
少し動かす度に、や、あ、と細切れの声が漏れる。
驚きを含んだ声音から、あまり後ろを触られるのに慣れていないことが分かった。慎重に拡げないと、傷付けることになりそうだ。
「ね。もうちょっと奥……、の手前側。撫でて、探して」
指を伸ばし言われた場所を探ると、ある箇所で一際高い声が上がった。柔らかな盛り上がりをなぞるように、指を動かすと、断続的に声が上がる。
きゅう、と指の根元が締め付けられ、得ている快楽の波が伝わってくる。
「……や、んぁ。すご、……ぜんぶ、届く……」
指を往復させ、内壁を掻くと、堪えきれずに声が上がった。
彼の陰茎に触れた時よりも、余裕が無さそうに声を漏らしている。俺を挑発するような彼が、触れる場所ひとつひとつに敏感に反応を返すのだ。
目の下は赤らんで、宝石のような色の瞳が蕩けていた。
「気持ちいい?」
「ん、うん……! すっごく……、ん、ぁ」
喉が勢いよく空気を吸い上げ、吐き出そうとすると嬌声が漏れる。白い喉が上下する度に、瞳が潤む度に、それらに触れたい衝動に駆られた。彼の中心は色を変え、吐精を求めて疼いている。
細い指先に、掴まった。
傾いだ顔が近づき、額に柔らかいものが触れる。あれだけ虚勢を張った人間が口付けたにしては、それは拙いものだった。
「一発、殴らなく、……って……済みそうだね」
震える唇が持ち上がる。視線の先は、俺の怒張を捉えていた。
「いくら奥手でも、据え膳くらいは食うさ」
下の口から指を引き抜くと、リジェが長く息を吐く。
肩を押され、寝台に倒れ込むと、細い脚が俺を跨いだ。服の裾から赤く熟れたそれが見え隠れし、熱を吐き出せずに揺れている。
儚げな指が肉棒を掴み、ほぐれきった場所に宛がう。
「……ん、…………う、っぁ…………」
ちゅぽ、と触れた部分が水音を立てた。
その感触を恐れるように、腰が一度浮く。何か言いたげに口が開くが、言葉を発することなく閉じられた。
体勢を変え、意を決したように腰を下ろす。えらが開いた孔に飲み込まれていく様が、服の裾越しに覗いた。一番太い部分が収まりきると、リジェの瞳がようやくこちらを向く。
「誰かさんが膨らませてる所為、なんだか、ら。……ちょっとは、手伝いなよ……!」
「……悪い。夢中になって見ていた」
頼りない腰を掴み、少しずつ引き下ろす。
同じように腰も動かせば、縁が捲れ、ずぶずぶと男根を飲み込んでいく。リジェは、信じられない、というように目を見開き、口を開けた。
「ひゃ……。や、なん、なんで…………!」
動揺して力が抜けたのか、自重で雄を含まされる。
青年が戸惑っているのをいいことに、その身体の奥深くまで自身を潜り込ませた。解れた内側は柔らかく、適度に締め付けながらも確実に異物を迎え入れる。
「や、あン、あ、もっと……ゆっくり……! ひゃ、うぁ……」
繋がりが深くなる度に力がみなぎるようで、更にこの身体を貪りたいという欲に駆られる。少し動いただけで体力を失っていたあの期間は何だったのかと思うほど、この青年を抱きたいという感情だけが身体を動かしていた。
奥まで辿り着くが、まだ全てが埋まりきらずに余っている。リジェはか細く息を吐くばかりで、受け入れるのに精一杯といった様子だった。
この調子では、この腹に思いを遂げられるまでに朝が来る。
腰を持ち上げ、せっかく埋め込んだものを引き抜く。その感触に嬌声が上がり、びくびくと躰が震えていた。
「倒すぞ」
身を起こし、代わりに彼をシーツに沈める。
脚に絡んだ下の服を脱ぎ落とすと、転がった脚を持ち上げた。茫然とした顔のリジェは、荒い息を整えようと呼吸するばかりだ。
腰が上がると、赤く濡れた窪みが露わになった。そこにあった杭が抜けたばかりの場所は、もう一度を期待するように震えている。
もう幾人もの男がこの場所を蹂躙したのだと思うと、何かが燻った。
その輪に先端を触れさせる。くっつけて、離して、それを何度か繰り返すと、くぷりと二度目の訪れは容易く招かれた。
「リジェ、もう……」
他の男と寝ないでくれ、と言ったら、笑い飛ばされるのだろうか。
腰を掴んで、全身で突き入る。緑の目が見開かれ、その縁からは濡れたものがシーツに落ちた。身を捩ると、長い髪がシーツに広がる。
「………………────ぁ、あ」
引き攣った喉は声を漏らす事しかできず、悲鳴に近い声は言葉を紡がない。
根元に近い位置が痙攣するように絞ると、その波を力を込めてやり過ごした。先端は柔らかいものが包み込み、根元は精を促すように輪を縮める。
「……急、に、こんな、入ったら、ぬけない……!」
少し身を退き、こつりと奥を叩く。
はくはくと必死で呼吸している様子に、嗜虐心が煽られる。腕を突き、指で探り当てた箇所を擦り上げた。
「……ぁ、うぁ、あ、あ……──ひ、んン…………!」
指先はシーツを握り締め、落ちそうになる快楽の淵から理性にしがみついている。その指が動き、俺の腕に添えられた。
先端が抜けるぎりぎりまで引き抜き、突き上げる。ぐちぐちと結合部からは音が立ち、粘膜の間で糸を引いた。
「いいとこ、当たってる、か……!」
「ひゃ、んぁ……! ────ん。きもち、い……!」
無意識に逃れようとする腰を、引きつけて穿った。小柄な身体に、無遠慮に欲を叩き付ける。
誰にでも一目惚れだと言って、軽率に閨に招くような性格ではない。初対面の男と、数時間後に寝台で睦み合っているなんて論外だ。
なら何故、この青年を抱いているのか。
「そうか。なら、良かった」
引いた腰を、叩き付けた。びくんと身体が震え、背が撓る。
「ぁ、ひ。ぁ、────あぁぁぁああああっ!」
「う。く、っは……」
身体を慮って、青年の中から己を抜く気は失せていた。
自身の欲のみで、粘ついたものを相手の身体の奥に吐き出す。肉輪が胴の部分を締め上げ、一滴たりとも逃さないとばかりに全体で絞り上げる。
自慰とは比べものにならないそれは、全身を波が突き抜けていくようだった。は、は、とお互いに荒い呼吸を整えようとしているのに、心臓は跳ね、血が巡っていくのを感じる。
呆けているリジェの頬に手のひらを添えると、ぱちり、ぱちりと飴玉のような瞳が俺を見た。
「ヴァレリー。きもち、よかった?」
「あぁ。俺は比較対象を持たないが、こんなに夢中になったのは初めてだ」
比較、対象を……、俺の言葉を反復したリジェは、ようやくその事実に思い至ったかのように目を瞠った。
彼が途端に慌てる理由が思いつかず、言葉を迷う様子を見守る。
「……誰とも、…………寝たこと、なかった?」
「恋愛下手だと言っただろう」
「うう……。娼館もあるしさあ。初めてが僕か……申し訳ないことしたな」
寛いでいた場所から自身を引き抜くと、ひゃ、と高く声が上がった。男根を扱いて最後まで吐き出したものを、シーツに落とす。
まあ、と顔を見ていられず、壁に視線を投げた。
「俺がそういう気分になったんだから、いいだろう」
そちらを見たりはしなかったが、リジェの機嫌が上向いたのを感じる。
腕が掴まれ、今度はごろりと身体を反転するように寝台に押し倒された。腕が寝台に押しつけられ、リジェもまた寝転がる。
「またしようよ」
満足げな顔に、気が向いたらな、とそう返した。
だが、二人してすぐに盛り上がり、その言葉は達成されることになるのだった。
翌日に出した朝食をリジェはいたく気に入ったらしく、仕事帰りにうちに立ち寄るようになった。
基本的には朝出勤して、夜には仕事が終わるような勤務をしているようだが、時おり夜勤という言葉も口に出る。
彼が来ると夕食を用意し、二人で食べて、たまに晩酌をする。翌日が休みの日は、リジェ自身が申告しては誘うので、身体を重ねるようになった。
誰かが自宅を出入りするというのは初めてのことだったが、不快にはならなかった。リジェは俺が静かに過ごしたい、と思っている時には話しかけて来ない。そして、俺が自分に興味を向けると、弾かれたように話を始めるのだった。
俺の過食の症状も、彼と付き合いが進む内に落ち着いていった。
食事量もほぼ元通りになり、栄養剤の分を食べずに済んでいるくらいだ。体調の変化を気にしてくれているのもリジェで、改善に向かっていることを誰よりも喜んでくれた。
擦り寄られ、一緒に過ごして、身体を重ね、気持ちを向けられる。
憎からず思っていたことも相俟って、明らかに俺は彼のことばかり考えるようになっていた。もう少しすれば休職期間も終わり、今までのように時間を作ることは難しくなる。
恋人という関係を望んだ方がいいのだろうか、最近はそればかり考えている。
その日は、通院を予定していた日だった。
医者には症状が治まったと伝えねば、そう思いつつ待合室で待っていると、すぐに自分の順番が来た。
診察室に入ると、座っていたのはあの時の老医師ではなく、もっと若い医師だった。俺は疑問に思いつつも、用意されている椅子に腰掛ける。
「ヴァレリーさん、来てくれて良かった。先日あなたを診たのは父なのですが、診療記録を見ていて、気になることがありまして……」
「あの、その事なのですが」
症状がもうすっかり治まっていること、薬の量を減らしたいと考えていることを告げると、医師は診察してみますね、と言って身体のあちこちを確認する。続けて質問をされ、それに対して回答していると、うん、と医師は頷いた。
「私は少し魔力の扱いに心得があるのですが、確かに、魔力は漏れていないようですね」
「……魔力?」
「いえ、あなたの症状を読んで、魔力を身体に留められなくなる病気を疑っていたんです。魔力というのは生命力でもありますから、栄養が抜け続けることに近い症状が出るんですよ」
医師の説明を聞けば、症状はあの時の俺が悩んでいた内容そのままだった。
「栄養剤でも対症療法にはなりますが、折角なら、治癒魔術師のいる大きな病院への紹介状を用意しようかと思っていました。治癒魔術師に身体の魔力の流れを整えてもらえば、完治する病ですから」
「治癒、魔術師……」
奇妙な符合に、何となく疑問が残った。
医師は栄養剤を減らしても構わないと言い、追加の薬が出ることはなかった。また症状が出れば今度こそ紹介状を、と話をされたが、俺は別のことが気になって、ただ返事をするばかりだった。
家に戻り、食事を用意していると、いつものようにリジェが仕事帰りに立ち寄った。
夜は流石に肌寒かったようで、家に入るなり瓶から酒を注ぎ始める。片手間につまみを出してやると、嬉しそうに受け取った。
無邪気な表情と、気負わず礼を言う性格を好ましく思っていることを実感する。
できあがった料理を皿に盛りながら、通院の話を切り出した。
「少し前に、過食に困っている話をしただろう。今日、通院して良くなったと話したら、もう薬は飲まなくていいと言われたんだ」
「へえ、良かった。会った時、ヴァレリーがすっごくやつれてたから心配してたんだよ」
にこにこと笑う表情に後ろ暗い所はなく、ただ治ったことを純粋に喜んでいるだけに思えた。それ以上何も言うことはないらしく、晩酌を続けている。
持った料理を食卓に並べると、酔っ払いの口から歓声が上がった。
「美味しそう! ヴァレリーの温かい料理が食べられるなんて幸せー」
「休暇が終わったら俺も忙しくなるだろうし、今のように頻繁には食べられなくなるけどな」
「そっか……、そうだよね。この家に来ても、ヴァレリーが帰ってないかもしれないんだ」
心情だけで言えば、合鍵を渡してもいい。
けれど、俺はリジェという名前以上の青年の素性を知らず、恋人とも名付けられない相手に合鍵を渡すのは憚られた。
どれだけ温かい食卓を囲めても、どれだけ深く繋がったとしても、教えてもらえない領域がある以上、俺たちの関係はここで行き止まりだ。
その夜は二人で料理をつつき、酒を飲み、夜が深くなる前にリジェは帰って行った。それからリジェの訪問はなくなり、俺の休暇はそのうちに終わりを迎えるのだった。
王宮に出勤すると、同僚の目の下に隈ができていた。
休みがあったというのに、すぐに仕事机に書類が積み上げられる。一段落したのではなかったのか、そう尋ねると疲れ切った同僚が口を開く。
「東部で大規模な崩落事故が起きたんだ。ちょうど工事中で怪我人も多かったし、大きな街道が埋まって使えなくなった。大きな案件から小さい事務手続きまで、急を要する書類がどんどん届くし、あちこちで会議も開きっぱなしだ」
「なるほど」
同僚は助かるよ、と差し出した手に書類を寄越してきたが、助かったのはこちらのほうだ。家にいては来なくなった青年のことばかり考えてしまう。仕事に忙殺されているのは有り難かった。
久しぶりの仕事でも慣れたもので、留まることなく手は動く。
「おーい。誰か、近衛魔術師に書類届ける人ー」
あちこちから手が挙がり、俺もついでに手を挙げた。座り続けていると尻も痛いし、今作っている書類の区切りもよかった。
「じゃあ今日はヴァレリーに。復帰初日だし、ちょっと休んでこいよ」
「ありがとう。気遣いが嬉しい」
そう言うと、同僚はぱちぱちと瞬きをする。
「お前にしては珍しいことを言うなあ。……これとこれ頼む。いってらっしゃい」
書類を受け取りつつ冗談めかして、いってきます、と言うと、やはり同僚は不思議そうに首を傾げて笑った。まあ笑われたとしても、悪い気分はしない。
王宮の廊下は長かったが、この散歩を楽しむべくゆったりと歩いた。家での休暇も悪くはなかったが、身体を動かす理由が与えられるのは楽でもある。
近衛魔術師の仕事場は警備が厳重な区画で、身体検査を抜けて、奥へと歩く。目的の部屋に辿り着き、扉を叩くと、中から返事があった。
同僚の名前と書類を持ってきたことを告げると、すぐに扉は開いた。
「あら、ヴァレリーさん。もう体調は良いのですか?」
相手の名は知らなかったが、その問いに頷く。
「ああ。魔力が抜ける病気に罹っていたらしくて」
「ええ!? 災難でしたね、頻繁に食事をしなければいけなかったでしょう?」
「そうなんだ。魔術師は詳しいな」
私達もそういうことはありますから、とその魔術師は言い、俺に同情する言葉を述べた。
「あれに罹ると、治癒魔術師のいる病院まで行かなければならないでしょう? 王都ならまだいいのですが、田舎では大ごとなんですよ」
「いや、……自然と治ったんだが」
「そうなんですか?」
魔術師は不思議そうに首を傾げた。
「あまり、そういうことはないのか?」
「ええ。奇跡的にそういうこともあるかもしれませんけど、治癒魔術師に任せるのが一番だと思いますよ」
医師に相談したときの、あの何とも言えない違和感が頭を擡げた。
リジェに会うまで治る余地などなかったというのに、彼に会ってから、不思議なくらい体調が良化した。
追うつもりのなかったリジェの素性が、気になったのはその時だ。
「ついでにすまない。酒場で知り合った魔術師で、リジェ、と名乗った者がいて、家に来た時に忘れ物をして帰ってしまってな。探しているんだが、心当たりはないだろうか」
魔術師はその名前を反復すると、うーん、と声を上げる。
「どういう方か、特徴は覚えていますか?」
「茶髪……にしては暗めの髪で、目の色は緑で、髪が長い男なんだが……」
「そうですね……。名前に聞き覚えはありませんけれど、その特徴を持つ魔術師で、魔術に長けている者、というのなら、モーリッツ一族の魔術師がまず浮かびますね」
俺がその姓を繰り返すと、魔術師は一旦机に戻り、何事かを書き付けた紙を持って戻ってくる。
「こう書きます。おそらく姓と名を合わせると、リジェ・モーリッツ。ただ、覚えている限り、王宮には該当の人物はいません。お力になれず申し訳ありませんが……」
「いや、助かった。大事なものだったようだから、返してあげたいと思っていたんだ」
すらすらと嘘が口をついて出ることに、罪悪感を覚えた。魔術師はそれは良かった、と言うと、話を切り上げる。もう一度、書類への礼を言って扉が閉められた。
預かった紙を見下ろす。
『リジェ・モーリッツ』
あんなに知りたかった彼の一部分が、本人の口からではないところで明らかになった。彼の本意ではないところで知ってしまったのだから、破り捨ててしまう方が正しい。
それでも俺は、紙を折りたたんで服に仕舞った。
終業時刻を過ぎても仕事は片付かず、同僚と共に書類と格闘していると、あっという間に夜も深くなった。そろそろ切り上げるか、と示し合わせ、帰路につく。
リジェがいない家に帰っても料理を作る気にはならず、酒場で食事をして帰ろう、と帰り道を変更する。酒場に行ったら、偶然リジェがいないだろうか、という期待もあった。
酒場の中は客で溢れており、見渡すものの、彼らしき姿はなかった。四人掛けの席は埋まっていて、カウンター席に通される。
料理をいくつかと、軽めの酒を頼むと、カウンターの中で店主が返事をする。店内に視線を向けながら待っていると、間もなく簡単な料理と酒が出てきた。
酒を口に含み、料理をつつく。
「そういえば、リジェさん今日は一緒じゃないんですかい?」
店主の問いに、顔見知りだったのか、と目を見開く。
人懐こい質ではあったようだから、彼がいないことを気にするのも分かる気がした。
「いえ。最近忙しいようで、時間が合わず……」
そもそも家に来てくれないのだが、真っ正直に言わずともよいだろう。俺は持ち上げた切り身を、そっと皿に戻した。
「ああ。最近はうちの店にも来てませんな。患者を放っておけずに忙しくしていらっしゃるのはいつものことですが」
「はは、そうですね」
店主の言葉に、リジェの仕事として思い当たるものがあった。
彼は、治癒魔術師なのだ。
腕はそこそこ、といったのは一般的な魔術で、俺に対して、彼は治癒魔術を見せてはいない。魔術の腕としてはそこそこでも、治癒の魔術に長けている可能性はある。
ぐい、と残った酒を喉に流し込む。かっと喉が焼けて、冷たい水が腹に滑り落ちていった。
魔力が抜け出ていく症状を見て、本職である彼がそれを見抜いていたら。俺が寝ている間に、もしくは、気づかないうちに彼が魔術を使っていたら。いや、あれだけ困っていた症状があの日を機に改善に向かっているのだ、彼以外の原因は思い至らなかった。
俺は、病を特定した彼に治療を受けていたのだ。
無言で食事を口に入れ、咀嚼する。大量にものを食べていた時と同じように、その時の食事は、味など、とてもしなかった。
────もし、もしもだ。
彼が本当に治療を目的に俺に近づいて、本当に善意だけで病気を治したのだとしたら。病の経過を気にして、会いに来てくれていたのなら。あの夜は、ただ酒に流されたのだとしたら。
きっと、合鍵なんてものは、永遠に受け取ってはもらえないのだろう。
あの後、モーリッツ一族についても調べることにした。
高名な魔術師を輩出している家系で、多くが貴族として生まれている。彼らは優秀な能力を持ち、複数の国で高い地位を得ている。
そして、リジェ・モーリッツ。
彼本人についても、魔術関連の本の中に名前が出てきた。
いくつかの有名な論文を発表しており、彼の顔も簡単に見つかった。載っていた姿は彼そのもので、生まれも、持ち得る能力も、ついでに言えば外見も含め、俺とは全く釣り合いが取れていない人物であることが分かった。
しばらくして仕事が落ち着くと、気がつけば彼のことを考えてしまう。けれど、気持ちを伝えよう、という気には到底なれなくなっていた。
もし告白して、一目惚れという言葉を真に受けたの? とでも言われれば、一生立ち直れまい。
あの甘い言葉は治療の一環だったとでも思って、いい思い出にすべきだろうか。そう気持ちが傾きかけていた。
その日は忙しかった仕事もようやく落ち着き、久しぶりにいつも通りの時間に帰宅することができた。体調もよく、ご無沙汰だった料理に取り組む余裕すらある。
二人分用意しようと無意識に計算してしまって、もう来るはずがないのに、と苦笑した。告白せずとも、自然と会わなくなるのなら、それが答えなのだ。
しっかりと失恋をしたのは久しぶりのことで、幼い頃を差し引けば唯一と言っていい。ざくざくと野菜に刃が入る度に、捨てる気持ちを思い返しては切り刻んでいった。
鍋に野菜を放り込み、蓋をして、あとは煮るだけだと手を放す。
戸棚から酒瓶を取り出し、洗ってあったグラスに酒を注いだ。
もう度数の心配をする必要はないのだが、リジェに差し出された種類の酒を未練たらしく選んでしまう。口に含めば甘ったるく、猫のような目元が思い起こされた。
ことり、とグラスを置くと、鍵置きが目に入る。
少し前に、告白に気持ちが傾きかけた時、合鍵に小さいぬいぐるみを結びつけておいたのだ。しかも、本人らしいな、と思った猫のぬいぐるみだった。
知人から土産として貰って仕舞い込んでいたそれを、渡す相手を想いながら、慣れない手つきでそろそろと結びつけた。
鍵を手に取って、外してしまおうと手に掛け、溜息と共に元に戻す。もう少し傷が癒えてからにするべきか。胸に手を当てながらそう思った。
玄関の扉を叩く音が聞こえてきたのは、その時だ。
追うように聞き慣れた声が聞こえてくる。俺は弾かれたように駆け出し、勢い良く扉を開け放っていた。
「よかった、今日は帰ってたんだ。いっつも帰ってなくて……」
言葉を遮るように、彼を抱き込んでいた。
夜道を歩いてきた所為か、服の表面は少し冷たい。抱き込んだ身体は細く、小さく、少し前まで馴染んでいたものだった。
え? と驚きの声が聞こえた事で我に返り、肩を掴んで引き剥がす。
「悪い。……飯、食べていくか」
「ありがとう、狙ってたんだよね」
リジェは俺の後を追って、部屋に入ってきた。まず酒のグラスを見つけると、僕も飲みたいなあ、と言う。
いつも彼が飲んでいた酒瓶を探すべく、戸棚の扉を開けた。目当てのものを掴み、引き出していると、近くで笑い声がする。
「ヴァレリーの鍵かわいいね。猫ちゃんだ」
鍵を持ち上げて見せてくる姿に、その鍵はリジェにあげようと思って、など、とても言えたものではなかった。
まあ、と歯切れ悪く返し、グラスに酒を注ぐ。
「あれ、でも別に鍵もある。予備の?」
「そうだな」
グラスを差し出そうとしたが、リジェの目は、食い入るようにその予備の鍵を見ている。どうした、と問うのを躊躇った。
「あの、さ」
珍しく言葉を迷う様子に、ゆっくりとその先を促す。リジェは猫の方の鍵を持ち上げて、こちらに向けて振った。
「…………最近、ここに来てもヴァレリーがいなくて、ちょっと待ってたりしたんだけど、全然会えなくって」
最近は崩落事故の後処理に駆け回っており、食事も終えてから帰ってくることが多かった。いつもリジェが来る時間よりも、もっと、ずっと遅い時間だ。
緑の瞳が潤んで見えて、呑まれないように視線を逸らす。
「鍵、欲しいなあ、って。僕が先に来た時は待っていたいんだけど、だめ?」
ぎゅう、と胸が鷲掴まれて、引き絞られる。
少し前だったら、彼の素性を知らずにいられたら。貴族の生まれで、腕のいい治癒魔術師で、俺とは釣り合わない人物だと、ただの愛嬌のあるだけの青年だと思っていられたら、どんなに良かったのだろう。
彼の手から、そっと鍵を取り上げる。
「いや……。さすがに、鍵、は」
鍵を渡してしまったら、気持ちの行き場を何処に持っていけばいいのだ。きっと、あの笑顔に期待しながら、生まれる感情を殺し続けなければ関係が保てない。
ぽつり、といつもは明るい声が、床に転がった。
「僕じゃ……。だめ、なんだ」
絶望さえも含んだ声に、慌てて表情を見下ろす。ぼたぼたと宝石の瞳から涙がこぼれ落ち、その量に驚くが、彼は声を上げたりはしない。
ただ静かに、両の目から涙を流しながら、茫然としている。
彼を蔑ろに立てた仮定が崩れ落ちたのは、その時だ。手を伸ばし、落ちる涙を拭う。それでも次から次へと落ちるものだから、その身体ごと抱き込んだ。
「リジェに、駄目なところはない」
「嘘だ……、だって鍵、くれな」
気が抜けたのか、ひぐ、としゃくり上げ始めた身体を、宥めるように撫でる。ぽんぽんと背を叩き、落ち着くまで服に涙を吸わせた。
しばらくすれば落ち着くだろうと高を括っていたが、リジェは次から次に涙の海を作っていく。
「なあ、リジェ。最初に会った時、一目惚れだと言ったのは嘘だろう?」
俺が問い掛けると、一拍遅れて、リジェの瞳から、だば、と涙が流れ落ちた。心外、とでもいうような表情に、動揺したのはこちらの方だ。
涙を拭いながら、収まるまで待つ。
「…………なんで、そんなひどいこと、言う……」
本人としては、嘘をついた覚えはないようだった。
「俺が病気だったから、声を掛ける口実に一目惚れだなんて言って……」
「口実、は! 病気のほう!」
リジェは叫び、うぁあああん、と身も世もなく泣き喚く。
口実は病気の方、とは、俺が真意を捉えられずに黙っていると、やがて落ち着き始めたリジェが、しゃくり上げながら言葉を続ける。
「……厄介な病気だって、そんな理由くらいないと、声を掛けたり……できなくて。だってヴァレリー、堅い感じ、……だし」
「顔見知りだったか?」
「僕、たまに酒場にいたじゃん!」
全然、興味持たれてなかったんだあ、と言いながらおいおい泣いている様子を見ていると、こちらが極悪人のような気さえしてくる。
そういえば、リジェのような男がいたような気はしたが、酒場ではいつも酒を飲んでいたし、その状態で覚えていられるかといえば怪しいものだ。
「一目惚れしたのは、もう少し、前。……で」
「つまり、嘘は言っていない、と」
腕の中の頭が、こくりと頷く。その後頭部を撫でながら、空中に視線を投げた。
おそらく貴族の出で、医師が気づきにくい病にすぐに気づけるような腕のいい治癒魔術師で、愛嬌のある性格の彼は、本心から俺に一目惚れをして、病気をいいことに近づいてきたのだという。
「俺の病を治してくれたのは、リジェなんだな?」
「ん。……気を遣うかと思って、こっそり」
「俺と寝たのは、酒の勢いで?」
そう問うと、リジェは急にぶん殴られでもしたかのように目を見開く。
「僕。ヴァレリーが一人目だって、言った…………」
「失言だった。だから泣くな」
色恋のための嘘ではなく、彼にとっては精一杯の口説き文句だったのだろう。
今の俺の反応を見て、全部から回っていた、と認識したらしい。俺の服の裾を引いて、抱きしめ返せもせずに、ただ滂沱の余韻に震えている。
息を吐いて、その手を取る。
開いた手のひらに、合鍵を載せて、握り込むように指先を閉じさせた。ぎゅう、と握り込んだ指先は、もう離さないとばかりに固く閉じられる。
「ありがと。都合のいい相手で構わないし、忙しい時は弁える」
ようやく口元に笑みが浮かび、腫れぼったい瞼越しに視線が合う。目尻を拭い、両頬を手のひらで包み込んだ。
「都合のいい相手にされると、俺が困るんだがな……」
顔を傾けると、瞼を閉じて背伸びをしてくる。啄むように唇が触れ、目を開けばあの緑が間近にあった。
「俺はリジェを好ましく思っているんだが、恋人では駄目か?」
ぽかんと口が開き、わなわなと持ち上げた指先が震える。間違っただろうか、と表情を覗き込むと、唇に縦の皺が刻まれた。
酒を一滴も飲んでいないのに、耳まで真っ赤で、視線がうろうろと彷徨う。
「ヴァレリーの恋人になれるの。……僕が?」
赤くなった目元に口付けると、ようやく手を背に回してくれた。滑らかな頬が擦り付けられ、全身で甘えてくる。
彼の口が言葉を紡ぐまで、俺は黙って待った。
「一目惚れしたから。……お、お付き合い、しよう」
酒場の時はもっと上手く言っていたように思うが、言葉は噛むわ、震えているわ、必死に絞り出したことが丸わかりだった。その様子に、ほっと胸を撫で下ろす。
誰かに釣り合っていないと言われても、彼がこんなに必死に求めてくれるのなら、それでいい、と言える気がした。
「ああ、こちらこそ。好きだ、リジェ」
俺の拙い言葉に、リジェは益々赤くなると、合鍵を握り締めて肩口に顔を埋める。
どう言ったとしてもこんなに大事に受け止められるのなら、口に出すのも悪くないものだと思えた。
しばらく会えなかったのは、俺とは全く関係なく、リジェも東部の崩落事故の影響で転院してくる患者が増え、対応に追われていたことが理由だった。
仕事も落ち着いたようで、また出入りするようになったリジェは、俺の家に入り浸りだ。
夜勤で会えなかった、と言っては朝方帰ってきて寝台に潜り込んでくるし、気がつけば服やら生活用品が増えている。
しかも、部屋の広さに余裕がある家で、物が多い方ではない俺の物置が丸々余っていることを知ったリジェは、目を輝かせ、大量の本を持ち込み始めた。
今の家狭くてさあ、と言う彼の家に行ったことはあるのだが、本、本、本、紙、紙、辛うじて服、という有様で、寝台以外で寛げる場所はほぼなかった。
食品も日持ちがしてすぐに食べられるものが多く、リジェが俺の家に来たがる訳を理解した。
ついでに掃除と整理を手伝ってやると、持ち込みやすくなった、と本が物置に置かれる速度が増す有様だ。
『俺たちが別れたら、これは持って帰らなきゃいけないんだぞ』
そう言ったのだが、リジェはまた目に涙を溜め、
『……ヴァレリーは、僕と別れるつもりなんだ』
と、本気で悲しがるものだから、俺の家の物置はリジェに譲り渡された。
後日、モーリッツ一族の話を聞く機会があったのだが、執着したものには一途、という気質が一族全体で共通しているらしい。身分が釣り合わない、と言われることはなく、彼の一族の気質を知っている人間からは大変だなあ、と同情される日々だ。
「やっぱ。僕の家いらないと思うんだよね」
ちらりちらりと視線を向け、同居を促してくる半居候は、ソファの上でだらりと読書をしている。
治癒魔術師としての腕はあれど、料理には才能を示さなかったらしい彼は、手伝う方が邪魔、と言って大人しくしているのが常だ。
はあ、と息を吐いて、いつも通りの定型文を返す。
「念のため、もう少しくらい様子見したらどうだ?」
恋人として生活を始めて、ひと月経っていないのだ。あまりにも早すぎる話だった。けれどそれを彼に言ったとしても、ひと月も経ったのに、と返されるだけだ。
ソファの住人は、ばたばたと脚を動かし、手元の本に栞を挟んで置く。
「様子見しなきゃ、安心できないような関係だって思ってるんだ……!」
「……………………そういう意味じゃない」
様子見を、本当に念のための様子見だとしか思っていないと伝えるには、果たしてどう告げるべきだろう。
必死に食い下がる姿が愛らしくて、つい口元から笑みがこぼれる。
新しい寝台を選びに行こうと思っていることを俺が口に出すまで、彼は目一杯拗ねて悩んで、そうして最後に種明かしを聞いて嬉しそうに笑うのだった。