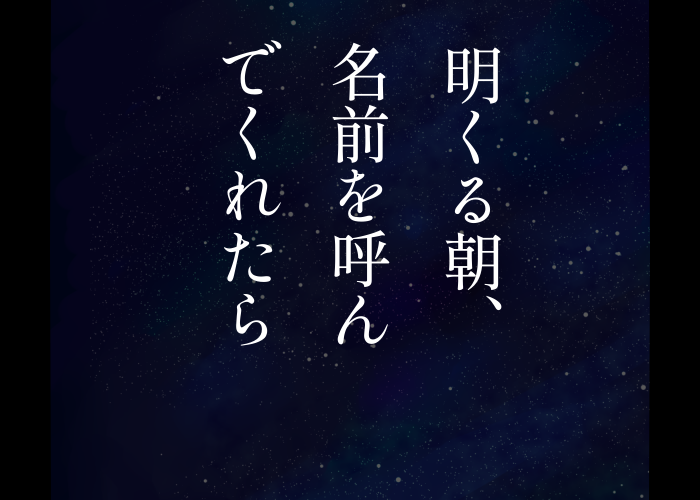「お気に入り」へ追加
「お気に入り」へ追加
【人物】
愛利 脩二(あいり しゅうじ)
支永 眞来(しなが まき)
愛利 始(あいり はじめ)
※注意※
※人によっては地雷を踏む話ですが、地雷の属性がネタバレに繋がるため書くことができません。地雷を踏むことに耐えられる方のみお読みください。
また、ハッピーエンドよりもビター寄りの結末です。
あの人、盆正月に休みがないんだもの、と愚痴る母親の言葉を聞き流しながらオレは兄がもういらない、と言った朝食を見やる。兄は少食で小柄だ。食事を、食べられない、とオレに任せてくることもある。
夕食は別々にとることが多いが、兄はきちんと食べられているのか、兄の小柄で細い肢体を見ていると不安になるほど兄の身体は痩せていて頼りない。指先は長く爪は几帳面に整えられていて、制服を纏った身体の腰回りは贅肉を纏えばもう少しふっくらするだろうに、兄の体型は兄の几帳面さを反映してか、変わることはない。
オレは食事を胃袋に流し込みながら、兄の言葉に相槌を打つ。
「さすがに今日は支永くん来ないかしら?」
長年の付き合いであり、幼馴染の支永眞来はうちの朝食時に紛れ込んでくることが多い。いくら幼馴染とはいえ厚かましい、とオレは思っているのだが、母はにこにこと笑いながら兄が要らない、と残した食事を与えてしまうので、支永は性懲りも無く毎日のようにやって来る。
そんな支永は朝に弱く、昔はふたりでよく起こしに行ったものだった。
「今日は眞来、遅いね」
「支永はいっつも朝遅いじゃん。来るんじゃない?」
「うーん、でも、ご飯冷めちゃう」
噂をすればなんとやらなのだろうか、母親の言葉を合図に、だだだ、と自宅には珍しく煩い足音が廊下を駆けて来る。オレはむすりと眉根を寄せ、兄はふふ、と対照的に笑顔を零した。
「どーもー、おはようございます! ご飯くーださーい!」
「しーなーがー! うっさい!」
母はうふふと笑ってどうぞ、と兄の分の食事を掌で示した。兄が要らないならオレが食べようと思っていたのに、とオレは味噌汁の椀を無駄に掻き回す。オレの隣の椅子を引いて腰掛けた支永は、いっただきまーす、と手を合わせた。
薄い茶髪にピアス、無駄に長い手足を惜しみなく活かすような黒のパンツとすっきりしたシャツ。手首には革のバングルが嵌っており、普段の大学生活でもこうやって全力でキマったファッションをする支永を、オレはこいつ暇なんだな、と評価している。
「今日の服、派手じゃない?」
「そうでもないって、大学には頭真っ赤とかいんだろ」
「そうそう」
支永の味方をする兄に、むっと頬を膨らませる。
兄は支永に対して昔から好意的で、よく甘えていた。オレがあまりにも兄のことを言うものだから、最近では支永と兄が会話することはめっきり減ってしまったが、昔は兄の方が仲が良かったくらいだ。支永はぱくぱくと勢い良くご飯を掻き込むと、打って変わって丁寧に魚の身をほぐす。
オレが食べきれない分の切り身を支永の皿に差し出すと、にかりと笑い返された。
「今日バイト?」
「や、今日休み」
オレが湯呑みを持ちながら雑に答えると、支永はオレも、と短く返した。
「植物園に行こうと思ってるんだけど、みんなで行く?」
「おー行く行く」
「僕はいいや。涼しいところで読書する、楽しんで来てね」
いつものことだが今日も、だらだらと支永と一緒に居ることになりそうだ。兄はごちそうさまでした、とオレと支永の会話を聞き終えると、リビングを出ていってしまった。
オレは兄と話をしたいのに、支永が入ると支永が会話の中心を奪ってしまう、すると必然的にオレは支永と会話をすることになり、オレと兄がゆっくり会話できるのは寝る前くらいだ。
「ごちそうさまでしたー、美味しかったです」
「いえいえ、助かるわ。こんな日にまでごめんなさいね」
支永は母に笑いかけられ、一瞬悲しそうな表情をしたが、普段通りの愛想のいい表情に切り替えた。オレは兄を追うように支永と連れ立ってリビングを出る。リビングの扉を閉めた途端、支永がオレの腰に手を回してきた。オレはべちりとその腕をはたき落とす。
いて、と大げさに手を振ってみせる支永を半眼で睨め付けると、ふん、と怒っているポーズを取りながら先を歩いた。
はは、と背後で笑う声がして、気を取り直すように肩に重みが乗り、オレは再三言っても叩いても聞かないスキンシップの多さに溜息を吐く。
「お前しか来ないなら、兄ちゃんと読書するんだった」
オレの言葉に、支永は口元を引きつらせた。
「あのなー、ブラコンもいい加減にして恋人とデートくらい純粋に楽しんでくれません? 全然外に出ないだろ」
「誰がコイビトだよ誰が」
「俺」
『支永はオレの恋人である』
らしい、と後に続くのだが、オレは支永と付き合うことになった経緯を覚えていない。今くらいの時期、支永と付き合うことになったらしい日の直後にぶっ倒れて暫く寝込んだためだった。オレは嘘だと言い張ったものの、支永の告白の前振りらしいメールだとか、オレがそれに返事をしているメールだとかを見せられながら説明された結果、どうやらそれは本当らしかった。
いくら暑さに浮かされたとしても、何故オレが支永と付き合うことにしたのかは全くもって不明だ。
「オレは兄ちゃんといたい」
オレは支永よりも兄ちゃんが好きだ。小柄で痩せていて、文系で大人しい兄ちゃんをオレと支永でずっと守ってきた。守りたいと思うのも、一緒にいたいと思うのも支永よりも兄ちゃんのほうがずっと上にあるはずだ。だから、支永と付き合おうと言われたとしても、頷くはずがないのだった。
だってオレと支永が付き合ったりしたら、今日のように兄ちゃんがひとりになってしまう。兄ちゃんがひとりになっている間に何かあったら、オレはどうしたらいいのだろう。
「でもお前は植物園に行きたいんだろ? いいじゃん、始はどうせ家でずっと読書してんだろうから、ちょっと目を離しても大丈夫だって」
「そうだけど……」
スニーカーを突っかけて、こんこんと玄関の床に叩きつけながら足を納める。ずっと一緒にやってきたのに、此処一年くらいこうやってずっと支永が付き纏ってくるようになって、オレは兄ちゃんと話す機会を取られてしまっている。
双子だったらずっと一緒だと思っていたのに、いや、ずっと三人でいるんじゃないかとすら思っていたのに、オレと付き合うようになった支永は兄ちゃんをライバル視でもしているのか、兄ちゃんと話さなくなってしまって、視線を合わせなくなってしまった。
オレはきっと、兄ちゃんか支永か選ばなくてはならないのだ。こうやって惰性で支永を選び続けていたら、オレは兄ちゃんを失うのだろう、と、ふとした瞬間に危機感を抱き続けている。
「お前が本当にずっと家に居て読書したいなら止めねえけど、……外、いい天気だぞ」
トーンを落とした真剣な声音に、オレはぐっと言葉に詰まる。
今此処でスニーカーを脱げば、オレが部屋に取って返しても、きっと支永は怒ったりしないのだろう。それでも、玄関を開けた先は暑いけれども、空は支永が言うように冴え冴えと晴れ渡っていた。
オレは支永には何も返さずに、黙って玄関から外に踏み出した。
植物園はオレと兄ちゃんと、支永にとっては常連の場所だ。年間パスポートなるものがあり、家からも近くにあったその場所は、昔は走り回るために連れて行ってもらい、成長してからはオレが見たい植物の開花時期にお弁当を持っていくようになった。
買い物などの寄り道を挟みつつ、二人してだらだらとコンビニで弁当を買い、植物園へ向かった。あまり客も多くない入園口で、年間パスポートを提示して園内に入る。
お目当ての場所も勝手知ったるというか、オレ達は他の花を見ながらその場所に向かった。辿り着いた先、目の前を桃色の色彩が埋め尽くす。
「うわ、咲いてんね」
園内ブログで写真では見ていたが、その時期よりも花盛りだ。オレは携帯を取り出すと、うきうきと近づいて構えた。遠目で一枚、近くで一枚、花まで背伸びして一枚とパシャパシャ撮影している間、支永は何も喋らなかった。
オレがあまりの静かさに居心地が悪くなって振り返ると、支永がパシャリ、とシャッター音を響かせる。
「……何撮ってんの」
靡く髪を押さえ、照れを誤魔化しながらそう言うと、支永はその様すらもパシャリと切り取った。
「いいじゃん、恋人と花と空。晴れて良かったな」
そう言いながらも支永はパシャ、パシャ、と撮影を続け、オレと百日紅の木を写真に納めた。オレがむくれてもその顔さえも写真に納めていた。オレはもう気にしないことにして、花に顔を近づけて匂いを嗅ぐ。色でも匂いが違うんだろうか、色の分華やかな気がした。
時間を掛けて我に返ると、オレが木の周りをぐるぐる回っている間に、支永は芝生の上に腰を下ろして一息ついていた。
「ここで飯にしよっか」
オレは支永の隣に座ると、ごそごそとコンビニの袋を取り出す。兄ちゃんなら手作り弁当だとかをぱっと作ってしまって恋人に差し出す所なのだろうが、オレはキッチンがあまり好きではない。
支永とだらだら新作の弁当だとかを見比べながら、これ、と選ぶくらいが性に合っている。
ぱきん、と歯で割り箸を噛み開く。
「エビフライ、うまそ」
オレが支永の弁当を覗き込んで言うと、支永は何の迷いもなく食べる前のそれをオレの弁当箱に乗せた。オレはそれを一口齧ると、うまい、とつぶやいて支永の弁当に戻した。でも何か物足りない、なんというか、エビフライはもっとサクサクしたものだ。
支永はそれを良かったとでも言うように、当然そうに残りのエビフライを口に放り込んだ。支永はオレがなにかくれと言った時にほぼ聞いてくれる。一年前からは、恋人だからとか言って更に思う存分甘やかすようになった。
「でも何でまた、百日紅を見に行きたがったんだ? お前ちっこい花のほうが好きじゃん」
オレは自分のハンバーグを咀嚼しながら、ぐっと言葉に詰まった。兄ちゃんの部屋にあった本を持ち出して栞のあたりを読んだら百日紅の悲恋の逸話があって、実際に見てみたくなっただなんて、支永に言ったらロマンチックー!だなんて言って爆笑されるような内容だった。
箸を振って、何でもない、と言葉を絞り出す。
「べつに、なんかいい匂いだって聞いたから」
誤魔化すようにそう言うと、支永はへえ、とそれ以上追求してきたりはしなかった。お互いにレポートの進捗だとかバイトの話なんかをしながら弁当を平らげると、ふう、と一息つく。支永がランチマットの端からビニール袋を引き寄せ、その中からデザート、と言ってプリンを取り出す。
やっぱり思う存分甘やかされている、と実感したオレがプリンを受け取る手を戸惑わせると、支永はずい、とオレの手のひらにプリンを押し付けた。
「最近オレが奢られてばっかじゃない?」
「俺が美味しいもの食って、ほわってなるお前が見たいだけ」
恥ずかしい、とオレが思わず呟くと、支永はそれでもいい、と笑って自分のプリンの封を切った。
「兄ちゃんも一緒だったら良かったのにな」
「俺だけでいいだろ」
顔を傾けて、キスの気配に目を閉じる。兄ちゃんが構ってくれなくなってから、支永はそれを埋めるように傍にいる。ずっと何か言いたげにしながら、ずっと何かを待っている。唇の感触はぼんやりしていて、膜越しにさえ感じた。
「最近さ、兄ちゃんが夜に話をしてくれる日が減っててさ。オレ、何かしたかなあ……?」
支永にもたれ掛かると、当然のように受け止めてくれる。ぽんぽんと背を叩く手のひらの大きさに、体重を預けてもいいのだと安堵した。
「いくら家族でも、いずれ離れるときは来るよ」
「支永はいるじゃん」
「俺は恋人だからいるんだよ」
それがあたかも当然のことのように、支永は言って笑った。
「な、『始』」
一瞬、その呼び名を素直に受け入れてしまいそうになった。僕は腕を振り上げると、ごつり、と眞来の頭に振り下ろす。
っだ、と濁った声が相手の喉から漏れる。
「何で兄ちゃんと間違える訳!? サイテー! さすがにオレ達が似てたって、呼び名間違えるって信じらんねー!」
「……ごめん、俺が悪かったよ。脩二」
真っ青になり、平謝りを続ける支永に、オレは最後には溜息とともに許す羽目になった。何故か、浮気だとか、そういった発想にはならなかったし、怒りもなかった。妙な違和感と共に、逆にそう呼ばれている方が正しいような、支永が必死に何かを誤魔化そうとしているような気さえした。
◇
愛利始という恋人がいる。
名前に間違いはなく、俺の恋人は間違いなくその名前である。ただし、俺の前で彼自身は全くそう名乗ろうとはしないし、彼が俺に名乗る自身の名前は『脩二』である。彼がそうなったのは、弟の死が切っ掛けだった。
大人しい兄と、活発な弟。対照的な二人であったが、その仲は良く、弟が兄に甘える姿は周辺では名物のようだった。そして俺もまた、二人と長い時間を過ごした。
本来の脩二が死んだのは心臓発作が原因で、キッチンで倒れている弟を最初に見つけたのも兄の始だった。あまりにも急な出来事に始の食が細り、引っ張られるように彼も倒れた。
目覚めた彼は自身を脩二と名乗り、今日も弟のように振る舞っている。昔より活発に出歩こうとしてはいるが、好みのものは変わらないのか、もとの始の部屋に忍び込んではよく読書をしているようだ。
俺達が付き合うようになったのも、一番の目的は、その記憶の齟齬を隠すためであった。彼は俺や家族以外に自身の名前を始と呼ばれても受け入れるが、弟の話を突っ込んで聞かれれば軽い錯乱を起こす。俺が誤魔化せるよう、常に一緒にいる関係を選んだ。
彼の両親にもそれは伝えてあり、思い出すように謝罪される。俺が本当に始が好き、というよりは、義務感で一緒にいることを選んでいると思われているようだった。
「支永?」
「恋人なのに、眞来って呼んでくんないの?」
「だって、ずっと支永じゃん」
嘘つき、ずっと眞来と呼んでくれていた癖に。
手を伸ばして、細くて小さな手を握る。そろそろと指が動き、握り返された。細い指も、身体も、ずっとそれらは始のままだ。弟だと彼が脩二を自称しても、変わらずに片思いしてきた、幼なじみの姿そのままだ。
「今日、俺の家、盆の里帰りで親が泊まりだからさ。……泊まっていったら?」
兄ちゃんが、で始まる断り文句を想像して、腹の中で笑う。兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん。ずっと呼ばれていた声を、始が大事にしていた証拠だった。俺は、ずっとその次だ。いつもよりも長い沈黙が続いて、ふと立ち止まる。
顔を覗き込むと、耳まで真っ赤だった。
「僕に何する気なんだよ! もう!」
ぼす、と腹を殴られたが、一瞬離れた手はまた繋がれた。真っ赤な耳をした始が、目の前でぐいぐいと手を引いて先導していく。辿り着いたのは俺の家で、泊まるんだよね? と言いたげにそろそろと振り返る視線が揺れる。
「手を出したりしないから、ゲームとかしよう。な」
そう言うと、ほっとしたような、残念そうな声がそれならいいけど、と言う。これが果たして病であるのか、いつ治るのかを俺は知らない。思い人は少し前に眠ったまま、まだ微睡みの淵にいる。たまにこうやって目を開けて、俺の心を掻き乱して、また立ち去っていく。
次に会うのはいつになることやら、間隔が短くなっていくのを予感しながら、小さな背を追った。