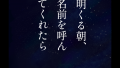「お気に入り」へ追加
「お気に入り」へ追加
※R18描写あり※
18歳未満、高校生以下の方はこのページを閲覧せず移動してください。
性描写が存在するキャラクターは全て成人済みです。
この作品にはオメガバース要素が含まれます。
【人物】
丹波 時雨(たんば しぐれ)
絡居 俊哉(らくい としや)
甘いものが好きになったのは、いつからだったのだろう。
特に変わった両親ではなかったと思うが、本当に小さいころ、僕が甘いものを食べるのは『おおごと』だった。父母の知人の家で甘い飲み物を勧められても、僕の分は父か母が断った。
両親は歯が悪くなる、というようなことを言っていた覚えがある。
ジュースにココア。コーラやサイダー。
代わりに甘くないお茶を受け取っては、飲めたかもしれない甘い味に思いを馳せた。
その件で両親と確執が生まれた訳でもないが、実家の仕事はアルファであり、人を動かすのが得意な兄が自然と引き継いだ。大学を卒業して数年経つ。オメガである僕は食い扶持だけを細々と稼ぎながら、日々を暮らしていた。
その日は、珍しくトレーニングウェアに袖を通す。
勤務先である和菓子屋で売れ残りが出て、喜んで引き受けた──までは良かった。けれど、傷みやすくカロリーが高いあんみつを短期間で食べたために、代わりに体重を増やしてしまったのだ。
休日に気合を入れて歩こう、と服を着替え終え、赤くなりやすい肌に日焼け止めを塗る。ぺたぺたと肌に触っていると、鏡の奥で不可ではないが可でもない顔立ちがこちらを見返した。
仕事柄、染めなくなった髪は黒々としていて、長くならない程度に保っている髪型はここ数年変わりない。仕事も落ち着いてきて、日々の変化が薄まりつつあった。
ボディバッグを持ち上げて廊下を駆け抜け、玄関でスニーカーに足を通した。立ち上がって数度跳ねると、身体はやはり重たい。
近くの公園は運動に特化した広めの場所で、そこでしばらく走るつもりだ。気合を入れ、勢いよく扉を開けた。
「うわ」
扉の先で、叫び声がしたのはその次の瞬間のことだった。慌てて扉を引くが、その隙間、視線の先に何かが転がったのが見えた。そろそろと扉を開けつつ、そこに立っている人物を見る。
「すみません。あの、急に……」
「あ、いえ。大丈夫ですよ」
目の前にいた男性は、僕ににこりと微笑みかけた。
薄い色の髪はやや長く、灰色のトレーニングウェアを身に纏っている。長身で体つきもしっかりとしているが、表情が柔らかいために威圧感はなかった。たまに郵便受けの近くで見かけるその人は、同じマンションの住人だろう。
男性はその場に屈みこむと、落ちた物体を拾い上げた。銀色の箔で包まれているらしいそれは、食べ物を包んだもののようだ。
「あ、ごめんなさい。落としちゃったもの、食べ物……ですよね?」
僕が彼の顔を見上げると、男性は拾い上げた物体に視線を落とす。表情のつくりさえ変えれば威圧感を与えかねない造作だが、その目は吊り上がることなく、垂れ気味に収まっている。
ドラマであれば、恋を引っ搔き回す役の色男のような風貌だが、それにしては所作がゆったりとしていて上品だ。
「アルミホイルの上にラップをしていますから、食べられますよ」
男性の手元にはトートバッグが提げられており、その中には溢れんばかりに銀色で包まれた物体が詰まっていた。僕がきょとんとバッグを見ていると、男性はその視線に気づいたのか、目尻を下げる。
「マフィンです。甘いものをどうしようもなく食べたくなって、作りすぎてしまいまして」
「ああ、分かります。……お弁当代わりですか?」
明らかに、お弁当用らしきトートバッグを眺めながら問いかける。その男性が持つにしては色鮮やかな印象の、赤い袋が揺れた。
「はい。ただ、食べなければと思って持ってきたものの、こんなに詰めても食べきれないか。その所為で落として気を遣わせて。面目ない」
「いえ、そんな。僕こそ──」
二人して、ぺこぺこと扉の前で頭を下げ合う。マンション内で見かけた時から思ってはいたが、物腰は柔らかく、怒っている表情が想像できない人だ。
そうだ、と両の指先を重ねる。
「落ちたマフィン、僕に頂けませんか? 後日、別のものをお返ししますので」
口に出しておいて、図々しい望みだっただろうか、と恐るおそる表情を見守る。しかし、男性は口元に笑みを浮かべると、落ちた包みとは別のものを持ち上げた。
差し出されたそれを、両手で受け取る。
「いくつ食べます?」
「ふたつ……? くらい」
重ねられた笑い声とともに、もう一つの包みが乗っかる。ありがとうございます、と反射的に告げると、いえ、と男性はトートバッグの上を閉じた。
「落ちたものを頂きたかったです」
「しっかり包んでいるから大丈夫。それより、……ええと、貴方も公園に?」
お互いに名前も知らないのだ、と気づいて、慌てて口を開く。
「僕は丹波といいます。丹波時雨」
「ああ、俺は絡居俊哉です」
話をすると、絡居さんは一階上の真上の部屋であることが分かる。生活音は煩くないか尋ね合う所から始まった話の間に、敬語も薄れていった。歳も近いようだし、敬語を使わずとも彼が相手なら怒られないような気がしている。
「──……なんか、話しすぎましたね。今から僕、公園で走ろうと思っていて」
「じゃあ、ご一緒しませんか。マフィンは一旦こっちで預かるから」
開かれたトートバッグに、受け取ったマフィンをまた詰め込む。明らかに数がオーバーしていて、口から零れ落ちそうだった。
その様子を見ながら、つい笑ってしまう。
「なんで詰め込んじゃうの?」
声は震えてしまい、笑み混じりのそれを噛み殺せはしなかった。つられたかのように彼の口角も上がる。
ぶつかりかけた時に大丈夫だ、と言いながら浮かべた笑みよりも、その笑みは自然に見えた。
「いや、入るかなと思ったんだ」
「僕のバッグに一個入るから、貰う」
はみ出ている包みを受け取って、自分のバッグに仕舞った。家から出て、鍵を掛ける。隣に並び立つと、やはり彼は頭一つぶんくらい背が高かった。
先導する背に続いて、階段を降りる。
「らく、絡居さんは……」
「言いづらいなら、下の名前でも構わないよ」
「イントネーションに迷っただけ。でも、……俊哉さんは」
「はい」
下の名を呼ばれて尚、素直に返事をする彼は怒る様子もなかった。
ここまで相手に気を遣わずに済むのは珍しい。人あたりが柔らかいとはいえ、体格といい容姿といいアルファのはずだ。それなのに、彼の匂いに攻撃的なところを嗅ぎ取れない。
それどころか、マフィンの匂いを纏っている所為で、甘党の口元には涎すら湧いてくる有様だ。
「運動がご趣味?」
「運動で体型を作るのも好きだし、せっかく運動で減らした脂肪を、美味い食べ物で増やすのも好きだよ」
「食べ物を作るのも好き……、かな」
「ああ。そっちもすごく好き」
へえ、と相槌を打つ。
僕は職場が和菓子屋だが、だからこそ自分で作ろうとせずとも、余ったお菓子を貰えることが多い。そうすると、自分で作ろうという気には然程ならなかった。
仕事も事務が主で、工場に入っても人手が要るような簡単な作業のみ。菓子に対しての知識はあるものの、和菓子作りのスキルは全く得られてはいなかった。
「作るの、楽しい?」
「今度一緒にやる? 砂糖を正確に量ったり、メレンゲを無心で泡立てるの楽しいよ」
「知らなかったな。楽しいんだ」
「音がいいんだよね」
音かあ、と僕が気の抜けた返答をするのに、俊哉さんは気にする様子もなかった。ただフラットで、この人に何をぶつけても反撃されないような気がする。すぐに名前で呼ぶことを許す姿勢といい、掴みどころがなかった。
アルファだと思った、認識自体が間違っていたのだろうか。
公園に着いてから二人して走ったが、基本的に運動能力が違うのか、並んで走るためには随分と手加減されてしまった。
けれど、しばらく走ってから休憩がてらつまんだマフィンと添えられた紅茶は美味しく、作ってみたい、と言った僕に対して俊哉さんはやんわりと受け入れて笑うのだった。
新しい連絡先が増えたのも、定期的に連絡を取るようになったのも、学生時代ぶりのことだ。
その日は、ようやく選んだ職場の和菓子を持参する予定を立てていた。いくら聞いても甘味の好き嫌いが絞り込めず、お返しまでには少し間が空いてしまった。
伝えていた通りの時間に部屋を訪れると、お茶を淹れるから、とソファに掛けるよう勧められる。
キッチンに入った俊哉さんは湯を沸かしはじめ、僕は手持ち無沙汰に部屋を見回す。
部屋の一角は、ラックに数台の筐体が並べられており、机の上には大量のモニタが並んでいる。部屋がやけに涼しく感じていたのだが、これだけ機械が並んでいれば暑くもなるだろう。職場でも、熱が篭もらないようにパソコンの埃を払うことがある。
湯が沸く音の合間に、機械音が僅かに耳に届く。モニタには大量のグラフが伸び縮みを繰り返しており、それらを彼が常時見ているらしいことが分かった。
「株とか……を扱うの?」
「ああ。株とかいろいろ」
「ずっと見てなくていい? 僕、見ようか」
「はは、ありがとう。短く見てなきゃいけないような取引はしないから、大丈夫だよ。画面は消し忘れ」
そう言って俊哉さんはキッチンを離れ、モニタの電源を落としてしまった。余計なことを聞いただろうかとそわそわしていると、キッチンに戻る際に頭をさらりと撫でて去っていく。
お茶を淹れている間、触れられた余韻に戸惑った。
「お待たせ」
中身は緑茶だというのに、容器は洒落たティーカップだった。
透き通った黄緑が、白いカップの底を爽やかな色で染めている。湯気の立つカップを預かり、鼻先を近づけた。ほっとするような緑茶特有の香りが立ち上る。
「ええと、デザートナイフでいいかな? とお皿だっけ」
キッチンから小ぶりのナイフとデザート皿を持ってきた俊哉さんの前で、包みを解く。持参したのは、切り分ける前の水羊羹だ。個包装したものも勤め先では売っているのだが、折角おとな二人で食べるのだから、普段食べない形の方がいいかと迷ったのだ。
念のため俊哉さんにも尋ねてみたが、『大きい方』と端的に賛成が返ってきて、一棹の水羊羹を手土産に持参することにした。
透明なプラスチックの箱に、淡い紫色が隙間なく詰まっている。容器を裏返して蓋に出すと、ふるりと水分を多く含んだ胴体が揺れた。
デザートナイフを借り受ける。
「厚さどれくらいに切ろっか?」
「四センチくらい」
堂々と言われるのだが、あまりにも細かすぎやしないだろうか。これくらい、と親指と人差し指を開いてみせると、うん、と頷かれた。
借りたナイフで切り分け、その腹を使って皿に載せる。どうぞ、と皿を差し出すと、両手で受け取られた。しみじみと皿を持ち上げ、外観を観察している。あまりにもずっと見ているものだから、流石に声を掛けた。
「あんまり放っておくと、水が出ちゃって美味しくないよ?」
「そうだね。いや、光に透かすと色が面白くて」
そう言うと、俊哉さんはようやくフォークを手に取った。そっと割って口に運んでいるのを流し見ながら、自分のぶんを切る。俊哉さんの言葉を借りれば『二センチくらい』に切り分けたそれを、皿に移した。
切り分けて口に入れた瞬間、舌にひんやりとした冷たさが届く。歯で噛むより先に口内で押しつぶされて溶け、含んでいた水分が広がる。飲み込む途中もつるりとしていて、羊羹のどっしりとした甘さとは違った。
続いてお茶に口に付けると味はさっぱりとして、砂糖のどれだけ入った餡でも覆い流せそうだった。クーラーの効いた部屋で、熱いお茶を飲むのもまた心地よい。
「瑞々しいのにしっかり甘くて、食べていて気持ちいいな」
言葉の後で大ぶりに切り分けられ、突き刺されたそれが大きな口に消えた。そもそも身体の大きさも違うのだが、マフィンをあれだけ大量に作ったあたり食べる方なのだろう。
静かに食べるのに、するすると口の中に食べ物が消えていく。
「俊哉さんの食べっぷりも見ていて気持ちいいね。余ったら半分こしよ」
「有難い。全部置いていってくれてもいいよ」
「え、やだ。……ちょっとだけ多めにあげる」
僕も明日の朝ごはんにするつもりだったので、その提案は却下した。くすくすと笑う俊哉さんは、皿が空になったため、もう一つ切り分け始めた。僕の朝ご飯は残るのだろうか。
フォークを置き、気になっていたことに対して口を開く。
「俊哉さんって、パソコン詳しい?」
「機体についてはパーツ交換するくらい。アプリケーションを作るのはちょっとだけ詳しいかも。でもまあ、趣味レベルだよ」
その答えに、自分の問いがざっくりしすぎていた事に気づく。あれだけ機械が並んでいるのだから、詳しいのだろうなと思っただけだ。
「仕事もそういうことをしてるの? ……って、答えづらかったらいいんだけど」
「別に構わないよ。所属しているのはネットワーク経由のサービスを提供する会社だけど、俺自身は商品を作る側じゃなくて、何かと調整する仕事の方が多いかな」
株とかいろいろを見ていたのは、仕事ではないのだろうか。僕が首を傾げていると、おいおい教えるよ、と俊哉さんは笑った。
「そっか、僕もパソコン使うよ。日持ちがするお菓子は通信販売をしてて、注文の対応したりするんだ」
「通販サイトとかがあるの?」
「ううん。メールと銀行振り込み」
「いいね。管理が楽ですぐに現金が入ってくる」
通販サイトを作ろうか、という話は持ち上がったことはあるのだが、あまりにも規模が小さすぎて、維持の手間を考えたら割に合わないという結論になったのだ。
それでもこの地域を離れた人から買いたい、という話があるため、小さなホームページに日持ちのする商品を載せ、注文を受けるためのメールアドレスが書いてある。
俊哉さんはスマートフォンで僕の勤め先のホームページを開くと、美味しそう、と呟いていた。
「今度、俺が店に買いに行ったら怒る?」
「なんで? 別に怒ったりしないけど、僕は主に裏方だから二階の事務所にいるよ」
「その方が気が楽でいいな。また来た、とか思われそうで」
別にそんなこと思わないけどなあ、と水羊羹をぱくつく。
まだじっくりとホームページを見ているあたり、俊哉さんは和菓子も好きらしい。一棹もある水羊羹を見ながら少年のように目を輝かせて食べるあたり、よほど変な選び方をしなければ何でも喜んでくれそうだ。
そんな俊哉さんが以前言っていたお菓子作りへの興味が、ふと頭をもたげた。彼が楽しんで作っているらしいお菓子作りというものを、自分も味わってみたくなったのだ。
「そういえば、この間のマフィンが美味しくて、僕も作ってみたいと思ったんだけど」
マフィンは大ぶりで、おおきく口を開けて噛み締めると、バターの香りとやさしい味が口いっぱいに広がるのだ。生地はほくりと容易く崩れ、飲み物を含みつつ食べ進めると、すぐに無くなってしまった。
「どういうお菓子が美味しくて簡単?」
そう尋ねると俊哉さんは視線を投げ、考え込むような仕草をした。適当に答えてもいいというのに、やけに慎重だ。
「マフィンが美味しかったなら、パウンドケーキとかスコーンとか?」
「いいね、美味しそう!」
こういうのとか、と続けて挙げられるお菓子はどれも美味しそうで、どれから作るか悩ましい。
「でも、そっか。クッキーとか揚げドーナツは、型買ってこなきゃ」
「ああ。いや、うちにあるから────」
貸してくれるのなら有り難い、と思いかけた僕に、降ってきたのは全く予想外の提案だった。
にこり、と柔和な笑みを浮かべる顔立ちは、見つめ合えばやけに整っていることが分かる。
「今度、うちで作らない?」
唐突な提案に、僕が勢いに呑まれて頷くのは数秒後のことだった。
頷いてしまった後、エプロン持ってないや、と逃げ道を探すも、俊哉さんはあっさりと俺も持ってないな、と言う。粉が飛ぶから汚れてもいい服でね、と言われ、結局その場で日程まで決めることになった。
さくさくとスケジュールを突き合わせて予定を決め、しばらく談笑して、じゃあまた、と部屋を出た時には、あまりの速度感に目眩がしたほどだ。
そういえば、お返しを持っていきたいと告げた後のスケジュール決めも、やけにスマートだったことを思い出す。このまま付き合いを続けていれば、恙なく次の予定も決まっていきそうだ。
気づかぬうちに、呑まれているような変な感覚だった。
それからお菓子作りの予定日より前に、予定が噛み合ってまた公園で走りもした。その時も、俊哉さんがお手製のドリンクを持参していた。甘酸っぱいレモン味のそれは、砂糖が調整されており、甘すぎずに美味しかった。
僕が美味しい、と言うと、いつもより表情を崩して笑う。その表情を見ると、舌に蜂蜜でも垂らされた気分になった。
「おじゃまします」
「お邪魔されます。どうぞ」
足りない食材を二人で買い出して、俊哉さんの家に上がり込む。温度の調整された部屋は、蒸し暑い外で籠もった熱をすぐに冷ましてくれる。
部屋に上がり込むと、俊哉さんは買い物袋を脇に置いて、食器棚を開け始めた。硝子のグラスを取り出している。続いて冷蔵庫が開き、カシカシと氷が擦れる音と、カランカランと落ちる音がする。氷が放り込まれたグラスに、手早くお茶を注いでくれていた。
ひんやりとしたグラスを立ったまま受け取り、礼を言って口を付ける。
「美味しーい! 生き返る」
「今日は暑かったからね」
ごくごくと半分くらい飲み干してしまい、一息つく。グラスを持ち上げ、表面が弧状に膨れた形状を物珍しく見やった。
「このグラス、形がきれい」
「結婚式のお返しでね。当時は二つも要らないと思ってたけど、いま役に立って良かったかな」
俊哉さんの言葉からすれば、おそらく、これはペアグラスと呼ばれるものではないだろうか。もう一度じっくり見ると、傷もなく、ピカピカに磨かれている。
新品らしきそれの片方を自分が使っているのが申し訳なくなり、視線をすこし下に落とした。
ぐい、と冷たいまま飲み干すと、脳がキンとする。
「ありがとう。作ってる間にまた飲みたいから、お茶もうちょっと貰っていい?」
「いいよ」
新しくお茶を注ぎ、少し飲んでからグラスを調理台の上に置く。
横にあった買い物袋を開けて、中身を取り出した。大抵のものは俊哉さんの家にあったため、ちょうど切れていた牛乳と、追加でチョコレートとホイップクリームを買ってきている。
飲み物を飲んで一息ついたらしい俊哉さんが戻ってきて、手を洗い始める。隣に並んで、ハンドソープを借りた。手を並べると、やけに隣の指は長い。
僕が開いた手を近づけると、意図を察したらしい俊哉さんが開いた手を添えてくれる。指の太さもそうだが、全体的に造りが大きいのだ。
「手のサイズ、こんなに違うんだね」
何か言おうとして、俊哉さんは考え込むように言葉を溜めた。泡だらけの手を水に浸すと、大量の泡が覆っていた掌がすぐに現れる。
「夜中に買い物とかする時は呼んでね。こんなに身体が小さいと心配になる」
「………………んー、ありがとう?」
「どういたしまして」
少し気分が浮上したようにそう言うと、流しの下から銀色のコップ状のものを取り出した。隣で首を傾げながら手を拭いていると、ホットケーキミックスを隣に置く。
「粉を篩います」
「これ、粉をふるうやつなんだ。へぇ……!」
取っ手を持ち上げると、底には網が張ってあった。ボウルを下に置き、ホットケーキミックスを入れた粉ふるいを揺り動かす。
雪が舞い落ちるようで、面白がりながらふるっていると、分量の粉がさらさらになった。横では俊哉さんが電子レンジでバターを溶かしている。レンジから取り出すと、乳製品特有のあまい匂いが立ち上った。
「混ぜるのに疲れたら交代しようか」
「はーい」
材料を次々に入れ、その度に泡立て器で混ぜ合わせる。調理器具はどれも装飾がシンプルで使いやすく、こういった物の収集を好んでいることが窺えた。
泡立て器がボウルの底を叩く度に、音ってこれのことだろうか、と彼の言葉を思い出す。金属がぶつかって、カツカツと音が立つ。人の手による不揃いな間隔、柔らかく触れ合うが故の金属音。それらは確かに耳を惹くものがあった。
途中で腕が疲れることはなく、先程ふるった粉まで混ぜると、生地がもっちりと纏まった。ひとまとめにしてラップで包む。
「少し寝かせなきゃいけないから、ちょっと休もうか」
「あ、そっか」
折角だからと調理器具を見せてもらい、次に何を作ろうかと案を出し合う。僕が調理器具を物欲しげに眺めていると、隣にいる俊哉さんが微笑ましそうに見下ろしていた。
「また作ろうか」
「ぜひ」
今日は簡単なメニューだったが、もう少し凝ったものも作ってみたくなった。そう伝えると、俊哉さんも満足げだ。
休憩にもならない休みは直ぐに過ぎてしまった。休ませた生地を綿棒で伸ばすと、俊哉さんが宝物を差し出すようにドーナツ型を手渡してくる。
そわそわと押しつけると、柔らかい生地が型の境界で沈み込んだ。輪形になった生地を持ち上げ、歓声を上げる。
「できた」
「うん、上手」
型抜き程度に上手もヘタもない筈なのだが、よくできたね、と褒めてくるので、疑問符を浮かべながらも受け入れる。
面白がって輪っかを量産する僕を、俊哉さんは手を出さずに見守っていた。
「天ぷら鍋あるんだ……」
足元の収納から鍋を取り出した姿を見て、やっぱり、とつい口に出す。
「収集癖なのかな? 基本的に物は要らないと思っちゃうんだけど」
確かに俊哉さんの部屋はすっきりとしていて、片付いているのもそうだが、全体的に家具も物も少ない印象だった。キッチンだけが扉を開ければ器具が出てくる、といった有様で、年季の入った趣味だと言うことを窺わせる。
「子どもの頃、パティシエ目指してた?」
「甘い物好きだったら、一度は目指すでしょ。でも、仕事にするは向かなかったな」
やはり年季の入った趣味だったらしい。余った生地を纏めながらくすくすと笑う。笑みが治まらない姿に拗ねるように、腕の外側を押しつけられる。
僕はオメガであり、フェロモンによる事故というものが常に意識の底にある。あまり人に接触しないように動いてしまうのだが、俊哉さんはアルファかベータであるが故か、誰かに触れることに気負いはないようだ。
触れられることに、嫌悪感は湧かなかった。
天ぷら鍋に油を入れ、温まった油にとぽりと生地を落とす。やがてじゅわじゅわと油が音を立て始めた。菜箸を持って、生地の間に距離を取らせる。
離して、寄せて。適切だと思われる距離を取りながら、最大限の数を放り込む。
「交代」
油の撥ねが大きくなると、菜箸は広げた掌に渡った。わざと僕の位置を下げるように身体を割り込ませるものだから、撥ねた油はこちらには届かない場所に遠ざかる。
「もっと、ひっくり返したかった?」
色が変わったドーナツの裏を眺めながら、俊哉さんが言った。まだその色は薄く色づく程度だ。
「ううん。気遣いが嬉しいほうが勝った」
振り返る視線から逃れるように、背の直ぐ後ろに回り込む。油の近くは少し暑くて、手を伸ばして少し氷の溶けたグラスを持ち上げた。こくり、こくりと飲み干して、息を吐く。
そこには沈黙があった。
箸先は動き続けるが、彼の唇は閉じて、言葉を発することはない。僕はグラスを持ったまま、まだ飲もうかと迷っていた。二人の間を、油が撥ねる音が埋めていく。耳を澄ますと、音の感覚が一定のように思えて、不規則であるのだと知った。会話みたいだ。
俊哉さんは鍋に視線を向けたまま、ぽつりと呟いた。
「俺は、────アルファだよ」
いつも通りの声だったが、その間には躊躇いが感じられる。振り返る素振りはない。ただ箸が生地を揺り動かし、鍋の側面を掻いた。
持っているグラスの側面から水滴が伝い、床に落ちる。
「怖がられるかもしれないし、気にしない人もいるから言うのは迷ったんだけど。たぶん、『時雨』はオメガなんだろうから、伝えないのは良くないと思って」
「そ……なんだ。何となく、そうじゃないかとは思ってた」
ぽたり、ぽたり、ぽたり。
水が落ちる音なんて響くはずがないのに、グラスの側面からの水が床を叩く度に、耳を音の礫が叩くように幻聴した。
立つ位置を変えられないまま、僕はその背中を眺める。
「もし、嫌じゃなかったら」
きつね色に変わった側を、くるりとひっくり返す音がした。じゅわ、と短い音が残る。
「体調が良くない時期に、買い出しが必要だったら言ってほしい。ドアの外に掛けておくくらいはできるから」
おそらく、僕がこれから連絡を絶とうとすれば、俊哉さんはそっと受け入れるのだろう。お互いに手の内を明かさないままでいることもできたのに、掌を広げて、それでも一線を踏み越えようとする。
「俺は、……これは俺自身の考えだけど、ベータじゃないという一点に於いて、俺は君を理解できる部分があると思う。だから、君が俺を頼るなら、力になろうと動くよ」
拳を握り込んだままでいることを、目の前のこの人に対して口を閉じていることを、僕が僕を許せなくなった。
その肩に両手を乗せ、ぽん、と一度だけ叩く。
「僕は、オメガだよ。いずれ発情期が来たら、匂いが届いちゃうかもしれない。その時はごめんね。それと、……しんどかったら頼らせてもらうかも。ありがと」
振り返った目尻は下がっていて、肩から離れた手が掬い上げられる。その手を鼻先に持ち上げて、す、と息が吸われた。
「この少しあまい匂いは、『その時期』に、どう変化するんだろうね?」
ぱちり、と目を瞬かせる。
「甘い匂い? そんなに頻繁には、甘いものは食べてないけど」
「おそらく、フェロモンの匂いが俺の鼻にはそう届いてるだけだと思うよ。香水は使わないよね?」
「俊哉さんと会うときは、使ってないよ」
アルファの中には匂いに敏感な人も多く、香水には好き嫌いがはっきりと分かれる。特に気を遣うような相手でもなかったし、会うときにそれらの香りは使わずに会っていた。
「今も、分かるよ」
自分の匂いを、はっきりと言われたのは初めてだ。どくどくと胸が喧しい。呼吸を繰り返していると、少し経ってやっと油の撥ねる音が風景に戻ってきた。
「オメガ相手にそういうことしてると、良くないよ」
「そうかな?」
「そう。あんまり触ると、誤解されちゃうんじゃない」
手を引こうとすると、指の先だけがまた捕まった。逃すつもりのない力が、指先にかかる。
掴めない人。そう思っていた相手の瞳が、こちらを捉えて揺れていた。
「別に、誤解ではないよ。すれ違って匂いが届く度に、小動物にでも引っ掻かれている気分だったから、切っ掛けを作れたのは幸運だった」
「………………」
「こうやって触っているのも、下心込み」
相手の指の腹が、僕の指先を撫でた。瞳が見ていられなくて、目を閉じる。しばらく闇に籠もって目を開くと、俊哉さんの顔が間近にあった。
反射的に身を引く。けれど、指先が掴まれていて離れられない。
「僕……、発情期に誰かを引っ掛けるようなタイプじゃないよ」
「知ってる。そういう子は俺、苦手なんだよね」
「俊哉さんが悪い人じゃないのは分かっているけど、戸惑ってる。恋人とかは……」
「それも勿論込みだけど。俺が君に誘っているのは、番の関係」
逃げても、すぐに追いつかれる。目の前の彼を、ベータだと思うのは難しかった。彼が言うように、そこにいるのは紛うことなきアルファだ。
瞳の鋭さも、隠す牙も、どう平凡に紛れ込もうとしても、違和感が残る。その違和感が、姿を現していた。
ごくりと唾を飲み込み、口を開く。
「…………ドーナツ、焦げちゃうよ」
ふ、と視線が鍋に逸れ、その隙に指先を抜き取る。手際よくドーナツの表裏を裏返すと、微笑む顔がこちらを向く。
「逃げられちゃったか」
「急に言われるから、びっくりするでしょ」
「テリトリーに入れた時点で、目的は明かしているつもりだったけどなあ」
言葉通りに受け取るなら、彼は誰彼かまわず家に招くような人間ではないということだ。僕の匂いに興味を持って、選んで引き入れた。
番の関係を、望まれている。
「だから、発情期に側に居ることを許したら、────覚悟しておいてね」
からっと揚がったドーナツは美味しくて、甘く匂い立つそれは大好きな味なはずだったのだが、胸がいっぱいでいくつかを持ち帰ることになった。
戸惑いを抱えたまま、僕は未だに俊哉さんとの付き合いを続けている。
まるで付き合ってでもいるかのように触れてくるようになった彼は、テリトリーに僕を招いては、甘いもので釣る。楽しくてつい一緒に過ごしてしまうのに、求められているのは番の関係なのだ、と時おり我に返るのだ。
断る理由が特に見当たらないのも、更に頭を悩ませている。
「時雨さんって、最近、生活変わりました?」
「へっ?」
職場の同僚にそう言われたのも、休日を俊哉さんと過ごすようになったある日のことだった。
梅芽さんは僕とは違って、一階の和菓子店の販売を主に担当している。年齢はそう変わらないが、落ち着きがあってしっかりした女性だ。
彼女と話すことが増えたのは、お互いにオメガだということを知ってから自然と仕事を融通し合うようになったからだ。友人というより、同士のような感覚だ。
この和菓子屋の店主夫妻はベータなのだが、娘に一人だけ、オメガとして生まれた子がいる。他の職場よりも体調が悪い時の対応には慣れているから、そういった理由で、オメガであることが理由で不採用とはならなかった。
「変わった……こともあるかも。なんで?」
「アルファに匂い付けされてます。あの、時雨さんって何かを断るの苦手でしょう、嫌だったら、本当に逃げてくださいね」
心配そうにこちらを見ている梅芽さんに、大丈夫、と笑いかける。それにしても、匂い付けとは、手首を鼻先に押し付けるが、匂いの変化は分からなかった。
俊哉さんの匂いというのは、甘かった覚えしかないのだ。その匂いを、僕の身体から感じ取ることはなかった。
「最近、上の階の人と知り合って。あの、この間、水羊羹を選んだときに言ってた人。あの人がアルファで、スキンシップが多い人だから匂いが移っちゃったのかも」
「スキンシップが多いの、匂い付けするためなんじゃないですか」
すぱりと言い切られた言葉に、僕は、う、と口ごもる。その様子を眺めて、はあ、と梅芽さんは息を吐いた。
「嫌いな相手ですか?」
「全然。食の好みは合うし、過ごしてて嫌じゃないし、……なんというか、気がついたら一緒に過ごしちゃうんだよね」
「それならいいです。けど、嫌なときは嫌だ、って口に出してくださいね。アルファ相手だからこそ」
瞳はまだ心配そうに僕を見ていた。こくりと頷き、ありがとう、と返す。梅芽さんは僕の背を叩くと、同情するような口調で言った。
「その匂い。私は怖い感じがしちゃうんですよね」
「僕、は、分からないからなぁ……」
「『アルファらしい』アルファなんだと思いますよ。番になったら裏切らないことをお勧めします」
店の準備があるので、そう言って梅芽さんは僕を大股で追い抜いていった。梅芽さんがいなくなってからまた手首を鼻先に当ててみたが、匂いが変化したようには思えない。胸の中に、絡まった糸を押し込められたような気分になった。
僕は諦めて歩き出し、事務室に向かう。事務室は和菓子屋の店主夫妻のどちらかと、僕を含めた事務員がいることが多いが、今日は昼過ぎまで僕だけだったはずだ。
タイムカードを押し、解放感に一度、伸びをした。
郵便物をチェックし、事務宛ての物は開いて目を通す。店主夫妻に確認が必要な物は、整理してそれぞれの机に置いた。
部屋の隅に置いてある領収書入れの箱から紙を拾い上げ、記載が増えた領収書台帳を持って席に着く。パソコンを起動させ、いくつかのメールに返信してから、伝票入力を始める。
ホワイトボードに購入しておいてほしいと書かれていた備品を発注し、途中、お客さんからの電話に回答していると、あっという間に昼になる。
上がいないため昼休憩は自由に取れるのだが、入力のきりが悪い。もう少ししたら梅芽さんに先に休憩に入らないか尋ねようと決め、パソコンに向かい直る。
しばらくして、階段を駆け上がる音が響いた。顔を上げ、事務室の扉に視線を向ける。
勢い良く扉が開き、梅芽さんが飛び込んできた。
「時雨さん。お客様に時雨さんの知り合いだっていう方がいらっしゃって、仕事の区切りが良かったら、会われます?」
「え? 誰?」
「たぶん、時雨さんが言う例のアルファの人です」
がたん、と椅子を蹴るように立ち上がり、わたわたとパソコンを操作してロックする。梅芽さんの後を追うように急いで店に降りるが、梅芽さんも早足だった。
店に入ると、こちらに向けて手を挙げているのは、間違いなく俊哉さんだった。駆け寄って彼の前に立つ。
「ごめんね。呼ばなくても、とは言ったんだけど、一応聞いてきてくれるって」
「わざわざ、どうしたの?」
「昼過ぎに関係会社にお邪魔する予定で、手土産を選ぼうと思ってね」
纏う薄いグレーのジャケットは形良く身体を覆っており、維持に気を配っているらしい体型をすらりと魅せている。髪型も整髪剤で整えられており、普段の髪を下ろした姿よりも落ち着いて見えた。
夏だからか首にネクタイはなく、中の黒のシャツも含め、品よくカジュアルに纏まっている。顔立ちの良さを存分に生かした姿は、休日に会うオフの姿よりも、アルファという感覚が強い。
しばらくぼうっと見惚れて、言葉を失っていた。
「……お菓子、何にしたの?」
「水饅頭。いつもその場で食べるし、珍しいものを持っていくと喜ぶ方なんだよね」
俊哉さんは手提げ袋を持っており、店での買い物は終わっているようだ。僕が手提げの中身を見ていると、俊哉さんは僕を見下ろして言った。
「お昼の休憩は取った? 折角だから、近くでご飯でもどうかな」
「お昼、はまだだけど」
ちらり、と梅芽さんに視線を向ける。今の時間から僕が先に休憩を取るなら、彼女の休み時間が後になる。彼女はそれでいい、と了承するように笑みを浮かべて頷いた。
「財布が手元にあるなら、今から行ってきたらどうですか? タイムカードは押しておきますから」
「誘った俺が奢るから、財布もなしでいいよ」
二人にそう言われ、ご馳走になります、とそのまま休みに入ることにした。梅芽さんに言われたことが気がかりではあったが、俊哉さん自体は今日も変わりない。
近くにいいお店はないか問われ、定食を出す店を挙げるとすぐに賛成された。店を出て歩き出す。
「忙しい時にごめんね。ちょうど時間があったから、会いたくて」
「急だったから驚いちゃった」
「嫌じゃなかった?」
嫌、ではなかった。会いたいような気もしていた。僕が知らないうちに匂い付けをしていくこの男が、どんな人物であるのか、もう少し知りたいような気がしている。
首を振って、歩みを揃える。
「俊哉さんのこと知りたいなって思ってるから。どちらかといえば、会いたかったかな」
「嬉しいよ」
そっと手が掬い上げられ、手が繋がった。
振りほどかずに素直に手が繋がったままでいる。僅かな体温の移り方にも、分かることがあるかもしれない。気温の所為で少し境が汗ばんだ。
二人で歩き、居酒屋に辿り着く。
昼の間はランチ営業しているこの居酒屋は、夜は海鮮が美味しい。ランチタイムには定食が出てくるが、居酒屋という造りが故に個室席が多く、じっくり話すのに適した店だ。
店の前に出ている日替わり定食の看板を前に、立ち止まった。
「日替わり定食がいい?」
「嫌いなメニューでなければ、絶対に日替わりがいい」
今日のメインは煮魚だ。
じゃあ日替わりにしよう、と言って俊哉さんは店の扉を開けた。流石に手を繋いでいるままでは通りづらく、自然と手も離れる。
「二人です」
店員がすぐこちらにどうぞ、と席に通してくれる。他の会社の休憩時間よりも少し前に入ったためか、まだ席には余裕があった。先に歩いていた俊哉さんが手前の席に座ったのを見て、向かいの席に腰掛ける。
水を持ってきた店員に日替わり定食を二つ頼み、水の入ったグラスを持ち上げた。俊哉さんは夜のメニューが気になるようで、お品書きを流し見している。
「日替わり定食の品数が多くていいね」
「うん。頑張れば食べきれる量だし、お魚だから胃もたれしなくていいよ」
ご飯にメインの料理、小鉢二つと汁物に小さいデザート。僕が梅芽さんと来ると、休み時間ぎりぎりまで居座ることになる。
俊哉さんはお品書きを閉じると、端に立て掛けた。
「オメガの子に言われたんだけど」
「うん」
俊哉さんは水を持ち上げ、ひとくち含む。
「僕から、アルファの匂いがするって。俊哉さんのことかなって思ったんだけど、心当たりある?」
「あるよ。結構、匂いが移るような触り方してる。敏感な人は気づくかもね」
悪びれる様子もなく、あっさりと肯定されて拍子抜けした。グラスを両手で握り締め、口を開く。
「なんで、そうしたの?」
「俺以外のアルファが君に近づいたとき、牽制したかったから」
答えは明快で、迷いはなかった。言い放った俊哉さんは僕を窺っている。この話を聞いた時に胸につっかえた絡まりを、解かずに押し込んでしまうこともできた。
ただ、この人に対して、やはり怖いものを僕には感じられないのだ。
彼が持つ怖いもの、は僕には向けられない。彼が番という関係を望むのなら、これからだって、きっとそのままの筈だ。
「僕。そういうのは事前に言ってくれないと嫌だな」
さて、怒られるだろうか。確信を持って俊哉さんを眺める。彼らしくなく目が泳ぐが、一向に怒り出す様子はなかった。
そうだろうな、とほっと胸を撫で下ろす。
「ごめん。でも、少し意図的に触っただけで、それをやめたとしても多少匂いは移るよ」
「俊哉さんが触らなきゃいいんじゃない?」
「それは……触りたいよ」
困ったように眉を下げる様子に、向かい側で短く笑う。
しばらくからかっていると、定食が二人の前に並べられた。俊哉さんは盆全体を写真に収めてお手拭きを使い、箸を手に取る。
真っ先に煮魚に箸を付け、ほぐした身を口に入れる。口角が上がり、咀嚼の間ずっと上機嫌だった。
「身が本当にふっくらしていて、口で蕩けるね。甘辛い味付けもいいなあ」
「だよね。白身魚だけど、ご飯がすすむ味」
一旦、会話が定食の話に移り変わる。
前回の定食の話をすると、俊哉さんは興味深そうに聞いていた。また別のメニューを食べに来たいようで、連絡をくれたら付き合うよ、と言っておいた。
食事を終え、サービスされたお茶を飲み終えてから店を出る。俊哉さんが会計をすると言うので、素直に任せて店の前で待った。
「お待たせ」
「おかえり、あれ。何か買ったの?」
俊哉さんの手には、店のレジ付近に並んでいるお菓子の箱が三つ握られていた。俊哉さんはその箱を僕に差し出してくる。
「これ。今日、時雨を呼んできてくれた人に二つ渡してくれる? もう一個は時雨が食べて」
「わ、ありがとう。梅芽さんも喜ぶよ」
果実味、バター味、のど飴の三つの箱が僕に手渡される。受け取った箱を、ポケットに仕舞う。
その後で行き先を確認すると、ここから職場までと俊哉さんの目的地は別方向で、店の前で別れることになった。
別れ際に、棚上げしていた言葉を思い出す。
「そうだ。匂いの件は別に怒ってはないんだけど、そういうのは、ちゃんとお話ししようよ。僕だって他のアルファを避けられるのはいいことだし、協力するよ?」
俊哉さんの目が丸くなり、それから口元が綻んだ。少し考えて、そっと両手を広げる。意図は察したが、飛び込むかは迷った。
僕の脚が動かないのを見て、広げられていた腕から力が抜ける。誤魔化すために唇が開かれようとした時、僕は少し閉じた腕をこじ開けるように飛び込んだ。
そっと背に手が添えられ、首筋に息が掛かる。
「もっとたくさん。匂いが付けられたらな」
ぽつりと呟かれた言葉は聞かなかったことにして、暑いことを言い訳に、しばらくしてそっと身を離した。
こんなに暑いのに妙に名残惜しかったのは、気の所為だったのだろう。
僕が俊哉さんの匂いを受け入れるようになると、更に触れ合いが濃くなった。抱き寄せられる度に、額や頬に唇を寄せられる。
その日は二人でポップコーンを作り、コーラをお供に映画を見ていた。
ふと、近づいた首筋から、甘い匂いがした。
近くに甘い食べ物はなく、匂いは花蜜に近いように思える。おそらく、これが彼のフェロモンなのだと気づいた。鼻先を寄せると、甘い匂いはやはり美味しそうで、首筋に凭れながら腹を減らした。
頭を撫でる指が心地よく感じてしまう。このまま踏み入れば、番になってしまう気がした。
「今日は、くっついてくれて嬉しいな」
ソファの上で脚の間に座らされ、厚い胸板が肩を支える。髪を触っていた腕が下ろされ、腰に巻き付いた。大きな画面にはアクション映画が流れており、視線はそちらを追う。
うん、と生返事をして匂いを吸い込む。
そろそろ、発情期が近い。匂いが分かるようになったということは、僕の鼻は、自然とこのアルファを番候補として視るようになったのだ。
画面から視線を外すと、僕を見ている視線とかち合った。
「……俊哉さん、僕の匂い分かる?」
「分かるよ」
手が取られ、彼の口元に引き寄せられる。すり、と鼻先を擦り付け、息を吸う音がした。指の間を相手の指が通り、お互いの手の腹をくっつけて、指先を絡める。
事前に抑制剤を飲んでいてもいい頃合いだが、まだそれを迷っていた。今使っている薬も体質に合わず、内臓への負担も大きければ気分も悪くなる。もし飲まずに済むのなら、そのほうが有り難かった。
ただ、その抑制剤を飲まない、という選択のためには、この人に負担を強いることになる。
「時雨が抑制剤を飲まずに過ごすなら、俺は付き合えるよ」
「まだ何も言ってない」
「言わなくても分かるよ。いつもより匂いが強くなってる」
うそ、と身を離そうとすると、力強い腕がそれを制した。また脚の間に戻され、頬を膨らませる。
長い指が、戯れるように頬を押した。手の腹で指を押し退ける。
「仕事、お休みさせちゃうし」
「スケジュールの都合が付くから言ってるんだよ」
俊哉さんは学生時代にとあるサービスの立ち上げに携わり、安定軌道に乗せた後で、サービスごと大手企業に買い取られたらしい。俊哉さんの今の役職はその企業での役職だが名誉職に近く、自宅か会社で仕事はするが、本人曰く『昔に比べればのんびりしたもの』なのだそうだ。
僕が発情期に入るのなら、自分も一緒に過ごしたい、と言って聞かない。
「もし、抑制剤を使わずに過ごしたら、すっごく楽かもよ?」
「……まあ、うん…………」
「今日からずっと、この部屋で過ごしたらいいのに」
あの手この手で一緒に過ごそうと誘ってくる。今のこの家の冷凍庫は美味しそうなものでぱんぱんになっていて、発情期に一緒に過ごすときに食べようね、と餌で釣られている。
ボードゲームで言うなら、完全に詰みだ。特に断る理由が見当たらずに困惑している。
強いて挙げるとするなら、これだけ押してくる相手と発情期を過ごそうものなら、この人を番に定めることになりそう、というくらいだ。
「さっき、俊哉さんから甘い匂いがしたんだ」
「本当?」
嬉しそうな声音に、つい笑ってしまう。うん、と頷いて、頬を相手の肩に擦り付ける。本能が矢印を向けているのだから、降参する頃合いかもしれない。
「僕も俊哉さんの匂い、分かるようになっちゃったなぁ」
「がっかりしないでよ。大事にするから」
本当に? と戯れに問い掛けると、本当に、と真剣な声音が返ってくる。
「じゃあ、今すぐシュークリーム買ってきてくれたら、今日からお泊まりする」
冷蔵庫の中にシュークリームがないことを、僕は知っている。背後の人は、ちょっと出掛けてくる、と器用にソファから立ち上がって、早足で駆けていった。
笑いながらその背を追いかけて、玄関で捕まえる。出て行こうとした身体を両腕で抱きしめ、嘘だよ、と呟いた。
そして、頻繁に入り浸っていた部屋に、その日初めてお泊まりをした。
彼の部屋で過ごし始めて、二日目の夜だった。
ぞわりと悪寒が走り、熱く息を漏らした。明日の仕事は無理そうだ。手早く梅芽さんに連絡を送るとすぐ、後のことは大丈夫です、と返信があった。
ほっと息を吐き、風呂に入っている俊哉さんに伝えるかを躊躇った。脱衣所の扉をゆっくりと開き、名前を呼べずに立ち竦む。
脱ぎ捨てられたシャツから、あの甘い匂いがした。指を伸ばし、服を拾い上げる。鼻先に当てると、身体を苛むぞわぞわが落ち着いた。すり、と頬に擦り付けて、指先を埋める。
夢中でそうしている間に、目の前の風呂場の扉が開いた。
「あれ?」
驚いたような声に、慌ててそちらを向く。言い訳のしようもなく、彼を見て、あ、う、と口籠もった。
俊哉さんは腕を伸ばしてバスタオルを引き寄せると、身体の水滴を拭う。謝罪と共にシャツを差し出すと、受け取って洗濯機の中に放り込んだ。
「匂いが欲しいの?」
「え……と……。そう」
わしわしと頭の水分を雑に落とし、置いてあったパジャマを着る。バスタオルを頭に引っ掛けたまま、俊哉さんは僕の手を引いた。口元には、牙を隠した笑みが浮かんでいる。
「おいで。もっと匂いがする場所に連れて行ってあげる」
向かったのは寝室だった。
部屋の扉を開けると、噎せ返るほどの俊哉さんの匂いで溢れていた。普段だったら意識することはなかったはずだが、今の身体は、その波に足元を掬われた。
繋いでいた手が離れ、抱き上げられる。身が竦んだまま腕の中に納まると、そのまま運ばれ、ベッドの上に下ろされた。
柔らかい布団の上に、身体が沈む。体勢を崩したのをいいことに、肩を押されて寝台に転がった。
「匂い、する?」
「うん。たくさん……」
茫然と息を吸い込むと、目を閉じた顔が近づいてくる。反射的に目を閉じると、唇が触れた。ちゅ、とリップ音と共に触れた唇が離れ、また重なる。
「ん、…………っく、ふ……」
呼吸をしようと開いた唇から、舌が滑り込んだ。ぬるりとしたそれが口蓋を撫でる。逃れようとした舌は絡め取られ、舌裏が舐め回された。
ふ、と息をする間も僅かに、また食らいつかれる。唾液が溢れて、口の端から垂れる。唇が離れるとようやく息をして、溜まった唾液を飲みこんだ。
「もっと、匂いがすることしない?」
軽口のように言われたそれなのに、口元に笑みはなかった。引っ掛けるように雑にボタンの掛かったパジャマに縋り付き、握り締める。
「……甘く、してね」
「余裕が残ってたらね」
覆い被さってくる唇を受け入れる。体温の変化からか、鼻に届く匂いもまた変化していた。
顔が離れ、胸元のボタンに手が掛かる。一つ、二つ。隠していたものが取り払われ、その部分の肌が顕わになる。食い入るように見つめてくる視線は強く、かりかりと爪を引っ掛けられているようだった。
首元に唇があたり、ぺろ、と舐め上げる舌の感触がする。
「…………ん。や、くすぐった……」
押し退けようと手をやると、その指先にすら舌を絡められた。声を噛み殺し、ひく、と息を飲み込む。
指の腹に歯が当たり、その鋭い先端が軽く食い込む。
「本当に、時雨の匂いはよく分かる。食べてるような気分になるよ」
指先が胸元に滑り落ち、先端の粒を摘まみ上げる。指の腹で捏ねられると、じわりと知らなかった刺激が伝った。
快楽の兆しを知られたくなくて、唇を噛んでやり過ごす。けれど、それさえも視線に捉えられているように指先はその部分を苛んだ。
「さっきから、くすぐったいことしかしない……」
「すぐ気持ちよくなるよ」
体温が上がって色づいた尖りが、相手の口内に消える。ぬるりとしたものが絡みつき、一瞬、強く吸われた。
喉の奥から漏れた声が長く抜け、指先が戦慄く。視界の先に赤い舌が覗いた。
「────っ、ぁ」
掌がぺたりと腹にくっつき、臍から腰をなぞる。生白い肌の上に、色の違う手が重なった。大きな手のひらに比べれば、全ての造りが小さく映る。
は、と熱い息が漏れる音がした。
「俊哉、さ……?」
「発情期の匂い、凄いな。頭がぐらっぐら揺れてる」
恍惚とした表情の前で、髪から雫が落ちる。明かりを背に、その顔には僅かな影が見えた。
指先が下の服にかかり、くい、と引かれる。促されるままに両手を引っ掛けて脱ぎ落とすと、伸びた指先が頭を撫でた。
ふと、思い出したように立ち上がり、ベッドの近くにある小机から買い物袋が引き出される。封が切られたばかりのチューブが引き出され、蓋を回し開けて中身を手に絞り出した。
ねとねとした液体を纏った指が、僕の股の間に伸びる。
「…………う、あ」
見ていられずに、手の甲を目元に当てる。自分のものではない長い指が、粘膜を擦った。人に触られることのない場所を、知らない手つきで弄ばれる。
反射的に股を閉じようと動いた脚も、もう片方の手で広げられ、固定された。
「……や、っあ、…………ん、は……ッあ……」
いつもは優しく頭を撫でてくれる指は、容赦のない刺激を与え続ける。ぐちぐちと濡れた音が撥ね、太腿が震えれば、それが合図とばかりにその場所を責められる。
自然と涙目になると、こつり、と額が重なった。
「俺、怖い? 辛い?」
「わ、かんな……。いつもなら、もっとくるしい、から。いつもより、は楽……」
ゆっくりと、ぽつぽつとだがそう伝える。そう、と嬉しそうに唇を上げて、顔が離れていった。
指先に潤滑剤が足され、脚が持ち上げられる。指は後ろに回り、合間を辿った。
窪みにぐっと力が込められると、指が滑りを借りて潜り込む。異物感に脚を動かそうとしても、別の腕に捕らわれたままだ。
「……っく。なんか、変なかんじが……」
「少し待ってね。探してるから」
探るように指が内壁を伝い、ぬちぬちと音を立てながら奥に向かっていく。ぞわぞわとした感覚が背を震わせ、シーツから浮き上がった。
そして、探されていた場所に指が触れる。
「────ッ、あぁぁっ」
内部から湧き上がるように、快楽が押し寄せる。男根を擦った時とは違った、知らない感覚だった。
縋るようにシーツに指を掛ける。指は抜かれることなく、弱いと分かった場所が長い指にばらばらに捏ねられる。
動きはゆったりとしているのに、定めた場所の周辺がくまなく刺激されていく。全身がその場所から快楽を拾おうと視線を向けていた。
「……ぁ、っあ。ぼく、それ……、────っ、う!」
「ここ。気持ちいいみたいだね」
指が挟み込むように、その場所を押し潰す。ひぐ、と息を呑んで、閉じた喉の奥でただ震えた。
段々と閉じる口の端に、近づいてきた唇が重なる。
見上げると、目尻が下がった俊哉さんの顔があった。のだが、普段の怖くないそれではなく、造り物めいたその表情を貼り付けた下から漏れ出すように、目の奥にあるのは笑みではなかった。
掌の中に隠れた爪は、こちらに刺さらぬように拳が握り込まれている。それでも、僅かに力を抜けば、手の隙間から光るそれが見え隠れするのだった。
「俊哉さ、……も、余裕、ないね…………。……、あン、っふ、ぁ……」
「はは、そうだよ」
後腔を拡げるように指が開かれると、くぷ、と濡れた音を立てて隙間が空く。その拡がりを確かめられる先に何があるのか、それを考えるだけで前がじくじくと疼いた。
チューブから滑りが足され、前後に往復する速度が増す。突き入るように指が奥を擦る度、閉じきれなくなった口から嬌声が零れる。
「……ぁ、あ、やァ、ん────! あ、ひぁ、……っく、うあ、あ、あ」
「ずいぶん熟れて柔らかくなったよ。ほら、分かる?」
「やっ、ぁ……! わ、わかんな……──ぁ、っあン!」
ずぷんと潜り込んでは、奥を引っ掻いて抜けていく。内壁を擦る指はごつごつとしていて、横で比べたあの指先であると分かった。指が上手く当たると、刺激に後ろが引き絞られる。
シーツの上で爪先を丸めれば、力が籠もって軽く滑った。
「時雨。いま俺ね、噛み痕付けたくて仕方ないんだよ」
「っん、うん……!」
「首の後ろ、俺に見せてくれる?」
一瞬だけ迷って、こくりと頷く。ちゅぷ、と名残惜しげに後ろから指が引き抜かれた。身を起こして、後頭部の髪を左右に分ける。身体を反転させると、相手が見えない心細さに手を握り込んだ。
「そのまま、うつぶせになって。…………そう」
申し訳程度に引っ掛かっていた上着が、背後から剥ぎ取られた。身体が寝台に倒れ込むと、腹に腕が巻き付く。自然と腰が上がり、腕と肩で身体を支えた。
吐息が首筋に掛かる。皮膚に牙が食い込み、がじがじと食感を確かめるように甘噛みされる。その間は、腕が両肩にかかり、強く寝台に押し付けられた。
「皮膚が柔らかい。大怪我にならないようにしないと」
「すぐ、噛む、の……?」
「ううん。苦いものは、甘いものと混ぜたほうがいいよね」
背後でぱさり、とパジャマが落ちる音がした。片手が太腿に触れ、背後に引かれた。
ぬるつくものが、尻の外側に当たる。買い物袋の中には、ゴムのパッケージは見当たらなかった。首筋を噛みたがっていたから、この触れ合いだって必要だと分かっていた。腹に手を当てて、そろりと撫でる。
粘膜ごと、触れられる。
発情期の目的通りのそれを想像すれば、脳が焼き切れそうだ。周囲には番候補の匂いだけが満ちていて、この場で他のアルファへの猶予を残しておく余裕もない。発情期より前なら、もっと噛まれることに悩む余裕もあったのに。
「まず、こっちを貰うよ」
くちり、と粘膜同士が触れ合って、一度離れる。シーツに爪を立てて、唇を噛んだ。腰を引き寄せられると、丸い先端が輪をくぐる。
指よりも質量の多いそれが、ずぶずぶと身体に挿入ってくる。長大なものが、内壁を削り取らんばかりに身体の内側を通っていく。
「────っ、ぁ、ぁあ、あ」
角度が悪かったのか、一度戻り、また腰を抱え直される。先ほど指で慣らされた処が、それよりも大きいもので押し潰された。
鼻先に届く匂いが、さらに濃く変化する。口を開いて、食べ物を飲み込んでいるようだ。押し引きを繰り返して、ようやく進みが止まる。
ふ、と背後でほっとしたように息が吐かれた。
「よかった。壊さなくて済んで」
冗談のような言葉だが、その声音は真剣で心から漏れたもののように思えた。体格差の所為か、ずっしりと腹に逸物が居座り、じわじわとした快楽がその場所から滲み出る。
粘膜で触れ合っている感触が、何よりも敏感に刺した。
「────っ、うあ」
ゆったりと引き抜かれ、押し上げられると、ずしりと重い性感が腹に留まる。一人で過ごす発情期に感じていた物足りなさは、完全に消えていた。本能で欲しがっていたものが与えられている。
子どもの頃に与えられなかった甘いものに、大人になっても執着している。それなら、ようやく与えられそうな番に、僕はどれだけ執着することになるのだろう。
「俺は、……多分。君という存在を、甘いって思うんだろうね」
「……ん、うん。僕も、……いま、ぜんぶ甘い」
腰を掴む手がつう、と皮膚の感触を堪能し、引き抜く動作に粘膜が絡み付く。力が加減できず、中で動かれる度に輪が窄まる。
勝手が分かりはじめたのか、ピストンの速度が増した。
「凄い、なこれ。中、吸い付いて……」
「あ、……っは、ぁああン、っあ、あ、あ」
パン、パン、と皮膚が打ち付けられる度、腹の奥を抉っていく。気持ちよさを拾える場所をまとめて刺激されると、全てが絡まって波のように押し寄せる。内壁がうねって、猛りを絞り上げた。
思考するより先に、身体はこのアルファの子種を待ち侘びている。肩を沈めて、腰を上げ、はしたなく全身で強請っている。
口の端から、涎が零れた。空腹に似た感覚だった。だからきっと、僕は彼の匂いを甘く感じる。
「時雨。……何でもあげる、だから、俺、と」
「ぁあ、も、だめ……ぁああ、い、ッ…………!」
腰に指先が沈み込み、一層強く、隙間なく突かれる。ぎりぎりまで引き抜かれた砲身はばつん、と皮膚を叩くように重なり、えらが奥にある門まで行き着いて、重なった。
身体が倒れ込んでくる。首に手が掛かり、首筋を持ち上げられた。
がぶり、と牙が首に食い込む。ばちばちと流れるものに痺れ、その痕跡から身体が書き換えられていく。
「────ッ、あぁあっ、ぁああああああぁあっ!」
ぴたりと隙間無くくっつけて、濁流が雪崩れ込む。生温かいものが、門から先へと流れ込んで、溢れた。
口を開けても、名残のような嬌声しか漏れなかった。噛まれているのに、痛みを感じない。前はいつのまにか果てていて、白濁を垂らしていた。
全身で押し付けられ、嚥下を求められ続ける。ひ、あ、と言葉にならない声が漏れた。 長い沈黙の後、首から牙を離す。ようやく、思い出したようにちりちりとした痛みが走り始めた。
「…………ご馳走様。美味しかったよ」
堪能した味を懐かしむように、その言葉は余韻を残した。身を起こす様子に、振り返って視線を合わせる。
ぺろりと舌舐めずりをする番には、美味しいお菓子を食べ終わった後の、満足そうな笑みが浮かんでいた。
すり、とシーツを掻いて、まだ腹に居座る肉杭を引き抜こうと動く。けれど、背後のアルファは僕を追い、僅かに抜けたそれさえも押し込んだ。
「…………っ、ひゃ」
「まだ食べ足りないな」
「ぼく、は、満腹で…………、も、い……」
「発情期の最初の内に慣れておいた方がいいよ。まだまだ、長いんだから」
まだ発情期の始まりでしかないことを示唆する言葉に、ひくり、と喉が鳴る。大きな掌が腹を撫で、背後でくつりと喉が鳴った。
やがて、またゆったりとした往復が始まる。
歯形の残った首筋に手を添え、息を吐いた。大好きな甘いものにも限度があるのだ、と、どう言えばこの番に伝わることだろう。
結局、甘い物好きの番は、甘いものは多いだけいい、と言わんばかりに、僕の言葉になど聞く耳を持たなかった。
ぱちり、と目を覚ますと、いつもと違うベッドだった。窓からは日差しが差し込み、空調は心地よく整えられている。
身を起こして、伸びをした。
身体は清められており、服も新しいものを纏っていた。あれだけ暴れ回ったシーツも替えられており、脚を動かすとさらさらと肌を滑る。疼く感覚も、何かを欲する衝動も落ち着いている。
ああ、発情期が終わったのだ、と明確に分かった。
首の後ろに手を伸ばすと、ガーゼが当てられ、布のテープで留められていた。この下には、くっきりと歯形が残っていることだろう。痛みはもうなく、かさぶたができているはずだ。
立ち上がって、寝室から出る。キッチンの方向からカチャカチャと音がしており、料理をしているのだと分かった。
「俊哉さん、おはよ」
僕を視界に入れた途端、番の目尻は下がり口元がゆるゆるになった。完全に懐に入ったのだろうな、とつられて緩んだ口元を押さえる。
「あぁ、おはよう。気分はどう?」
「何だろ。……爽快、かな」
「なら良かった」
サイズ違いのパジャマを引き摺り、ぺたぺたと床を歩いた。
番に近づき、何かを作っているらしい手元を背後から覗き込む。彼の手元では、きつね色に焼き上がった生地に切れ目が入り、クリームが絞り出されていた。
丁寧に絞り出されたそれが、切れ目から溢れんばかりに顔を覗かせる。
「このまま食べたら?」
はい、と素のまま差し出されたそれを、両手で受け取る。見た目も匂いも、間違いなくシュークリームだった。
返事をする事もなく、本能的に齧り付く。
香ばしい生地がふんわりと歯に当たり、奥から甘いクリームが流れ込んでくる。バニラの香りで口の中がいっぱいになった。クリームが零れないよう、せいいっぱい咀嚼を繰り返す。
「おいひい」
「はは。クリーム溢れてるよ」
口の端を親指で拭われ、その指が相手の口に消える。
美味しい、と呟いた俊哉さんは、もう一個も同じようにクリームを絞り入れ、自分の口に放り込んだ。大きな口で食べれば、ぺろりと無くなってしまう。
「もう一個」
横から抱き付き、そう言って強請る。
僅かな発情期の名残らしき匂いが、甘いクリームに混ざって鼻先に届く。もう、この匂いは僕だけしか拾えない。静かに、満足感に酔いしれた。
「キスしてくれたら、もう一個あげようかな」
「うん!」
肩に手を掛け、爪先を伸ばして頬にキスをした。笑い声の後、ふわふわの生地を口に押し付けられる。
囓って溢れ出すクリームは、いつもより甘ったるかった。